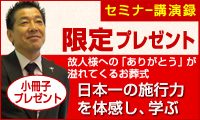2014年4月2日 22:40
「隠れ家」その2・・・。

先日同様、
席が埋まってないでしょ?(笑)
「隠れ家に、繁盛店なし」
↑↑
どうでもいい、オヤジ格言。
客が少なく、
話し声の大きな輩がいないこと。
それは「隠れ家」の外せない条件なのです。
あまりにも「隠れ家」すぎて、
「店がなくなってしまうかも・・」
そうゆう心配はつきまといます。
現に、さみしい思いをすること、しばしば。。。
俺が行くときは、客が少なく、
行かないときだけ、何とかして、稼いでおいてもらう!
これが理想のパターン。
余裕あるオーナーが、趣味でやってるとか、
裏で、ネット通販で稼いでいるとか、
そんなのも、いいですね。
ついでに、色々な、付帯条件をつけてみたいと思います。
スタッフの数が、多すぎるのは、駄目です。
注文したのに、なかなか出てこない、、くらいが丁度いい。
レイアウト的に、スタッフと目が合うのも、駄目です。
シアトル系のカフェみたいな店員教育は不要・・・。なんなら、水も勝手に入れるから。
声の大きな人が好きそうな「週刊誌」があると、次から行かない。
人目をはばかり、ニヤつける「フライデー」は、OKだ!!
本当は、スポーツ新聞が、あると嬉しい。。。
「報知」以外ね。原監督は好き、でも巨人の負け試合が好き。かといって、阪神好きなわけでもない。
オヤジのわがまま与太話に過ぎません。。。
申し訳ありません。
・・・・
中西正人をキライになっても、
日本売上アップ研究所をキライにならないでください!!
(前から、言ってみたかっただけです・・・。
「春になってきたんだなあ・・・」
「幸せなヤツだなあ・・・」と、お見逃しください)
次から真面目にやります!!
2014年3月30日 14:33
休みの日のひとコマ・・・。

隠れ家としているカフェに
パソコンとノートを持ち込んで、、、
美味しい珈琲を片手に、
静かな時間のなか、アイデアや構想が生まれる・・・。
「エグゼクティブには、そうゆう時間が必要」と、書籍には載っているし、
そんな、ビジネスマンに憧れてもいるのです。
でも、理想と現実は、違う・・・。
こんな上質な空間で、生まれた例がありません。
ワタシの場合。
良いアイデアとか、将来構想は、
切羽詰った状況において、とか
何とかしなきゃならない窮地に追い込まれて、とか
誰かと話していて、、というときに、生み出されます。
一生懸命、仕事しているとき。
脳ミソ・カラダ、フル回転しているときにこそ、生まれてくるのです。
きっと、貧乏性なんですね。
じゃあ、隠れ家カフェで何しているかというと・・・
こんな本や雑誌の誘惑に負けてしまい、。

「世界の路地裏」!最高です。
しかも「新・世界の・・・」。
(笑)
「意思薄弱」と「貧乏性」に効く、特効薬はないものでしょうか?
2014年3月27日 6:48
月のうち、宿泊の出張が、最低でも7~8日になります。
ホテルにチェックインしようとすると、
予約した料金のままで、
ゴージャスな部屋に案内されることがあります。
「本日は、私どもの都合で、
特別にエグゼクティブルームのほうに、ご案内させていただきます」

その日は使う可能性がとても低い「遊休施設」は、
部屋の清掃時間を、通常の時間と同じで仕上げることさえできれば、
基本的に、発生するコストは、同じです。
余分なコストがかからず、
お客様にご満足いただけることであれば、
どんどん、目の前のお客様に、できるだけのサービスすれば良い。。。そう思います。
「払った料金以上のことをしては、高い料金を払ったほうのお客様に失礼だ」
「通常の価格が、値崩れを起こしてしまう」
こんな心配をして良いのは、ごく一部の超・高級商売をしているお店の話。
ここに憧れて、大衆向け商売のお店が、
ツンケンしたところだけを、真似する必要はないんじゃないかなー。
葬祭業界では、特に、当てはまることが多いと思います。
コスト同じで、できるサービスが、たくさんあります。
「ふふーーーん、特別扱いしてもらっちゃった!、また今度もここにしよう!」
「きっと、俺が、お行儀良さそうに見えたから、サービスしてくれたんだな。」
こんな風に思うのは、私が、単純かつ、ノー天気すぎるから??
どうなのでしょう??
遊休資産(施設・備品・人間・・・)の有効活用、
考えてみてはいかがでしょうか。
2014年3月22日 21:02
春の陽気が近づいています。
梅の花が満開、やがて、桜の季節へ。。。

葬儀社にとって、冬の書き入れ時が、ひと段落し、
次は、会員募集のために、本格稼働するシーズンがやってきます。
ご年配の皆さんが、動きやすいのは、
なんと言っても、春と秋=気候の良いとき。
コンサルティング先で、
葬祭ホールを開放しての集客イベントが、これから本格化してきます。
今年の春の土日の友引。。。と言えば、
4月5日(土)、
5月3日(祝)、
6月1日(日)、
6月7日(土)。
このあたりが、イベント最適日ということになります。
今年は、4月・5月に、最適な日が少ない。
6月も、中旬になれば、梅雨に入ってしまうし。。。
イベント予定日は、
なんとか晴天になって欲しい。
いつも、祈るような気持ちになります。
予定日前には、何度も、インターネットの週間天気予報にアクセスしてしまいます。
ご支援先の社長と同等か、それ以上に、御社のことに真剣です!
準備を万端に!
そして、好成績の報告を、心からお待ちしています。
2014年3月18日 10:51

クライアント先に同行した際の、
当社・経営コンサルタント・佐伯泰基です。
女性スタッフ、パートさんまでも含めた、営業会議での雄姿です。
しばらく見ないうちに、
独自の成長を遂げていました!
本当に言いたいことは、(ささやくように)小声で言う。
・・・「この一言だけを、お客様にお話しいただくだけで、大丈夫なんです」
・・・「3月の売上は、皆さんにかかっています」
身を乗り出して言う。(机の真ん中に、アゴがつかんばかりに)
むむむーー!
表現方法を、勉強して実行しているそうです。
すでに、スタッフさんの心をつかんで、実行してもらうのは、
彼の方が上手かも。。。
注意散漫な、おしゃべりスタッフさんも、
魔法にかかったように、じっとおとなしく聞いていました。
佐伯のトリコです!
2014年3月15日 22:53
大阪では、注目の人間ドッグだから、
コンサルの参考になることを、持ち帰ろうと、
頭脳フル回転で、徹底観察!
きょろきょろ・ウロウロ・・・
でも本来、こんなケチ臭い人間のための空間では、ないんでしょうねー(笑)
ここが待合スペースです。

施設の雰囲気づくりのための照明やカラーリング、
各種内装材の使い方は、葬祭ホールづくりと、ほぼ同じです。
さすがに、素材は、良いクラスのものを使っています。
ここまでコストをかけなくても、ホールの雰囲気は作れそうだなー。
さて、問題は・・・コストをかけずに、
すぐに、葬儀業界に応用できそうなことはないかな・・・と、
書き留めたことを、順不同で、ご紹介いたします。
1・以前の出来事にふれる
健康診断を直接、窓口申し込みしたのですが、
「先日は、ご足労いただきまして、誠にありがとうございました」と、
別のスタッフが声をかけてきます。情報共有の「PR」ができています。
2・名前を呼ぶ。とにかく数多く、呼ぶ
「中西様、少しチクッとします」「中西様、大きく息を吐いてください」
「中西様、終わりました、起き上がってくださいませ」
3・ギャップのある衣装・服装
なんと、看護婦さんはスーツ姿です。。
採血も血圧測定も、スーツ姿。常識と違う点がいいですね。
4・院長が自ら、あいさつに来てくれる
事前の説明を受けている最中、
「ようこそ、いらっしゃいませ・・」と、顔を出してくれます。
これは、悪い気分、しないですよね。
5・顧客情報に対して、個別の対応
着替え用ロッカーの中には、私のサイズにぴったりの
LLサイズの検査服が入っている。
6・雰囲気にあわせたBGM
館内には、BGMとしてクラシック音楽が流れています。
7・ここでわかる検査の結果は、当日のうちに知らせてくれる
健康かどうかを知りたい・・・という目的に対して、
すぐに教えてくれる。「スピードは、サービス」。
8・はじめて会うスタッフは、自己紹介をする
「放射線技師の●●です、本日はよろしくお願いいたします」
「基本検査担当の○○です・・・・」
9・これから起こることを、事前に説明する
「この検査は・・・を目的としていまして、このように行います。
時間は〇分くらいで終わります」
10・これでもか!というくらい、気遣う言葉をかける
「お足下、お気をつけくださいませ」
「寒くないですか?」 「お手洗いは、大丈夫ですか?」
葬祭業界でも、できることが、たくさんありますよね!
個人の技術や感性にまかせるだけでなく、
会社のルールとして実行する「接客システム」へと高めてゆけそうです。
<番外編1>
この人間ドッグ、、、コンサルタントが入っているな~。たぶん。。
そうゆうニオイがするんですよねー。
フツーの病院ができる接客じゃないです。体系化された教育ができています。
誠に勝手ながら、気がかりは・・・患者数が少なそうなこと。
マーケティング面は、
当社にまかせてくれたら、どかーんと、患者さんを集めますぜ!
<番外編2>
初めて体験しました。胃カメラを。
この世のものとは思えないくらい、つらかった―!
汗ダラダラで、苦しみ耐えているのに、
漫画家みたいな女医ちゃんが、、、
モニター見せながら、
「キレイです!キレイですー!」
「十二指腸も、すごくキレイです!」と
人の胃の中を見て、歓喜の声をあげる。
・・・・くっそ~~。それどころちゃうねん!どうでもええねん!!
「コ、コ、ココロのなかもキレイなの、わかります?」、
半死半生の状態で、漫画家に対して反撃を試みる!!
、、、
「それは、わかりませんね」
冷やかに、撃退されました。(涙)
2014年3月14日 21:48
みなさん、健康診断って・・・受けていますか?
「忙しいから!」
「俺、体力には、自信あるから!」と、
実は、ここ6年間くらい、健康診断をサボり続けていました。
12月~2月、葬儀社の皆さんが忙しくなる時期は、
我々、コンサルティング会社は、ヒマになります。
暖かくなってくると、
施行が落ち着いてくる分、
コンサルティングのご依頼が増えてきます。
「なんとか、冬場のうちに、健康診断に行ってこよう・・・」と、
思っていたのですが、想定以上に冬場も忙しく・・・。
3月に入ってから、
なんとか、時間を確保できたので、健康診断へ。
6年ぶりだし・・・と「人間ドッグ」に行くことにしました。
最高の空間とサービスを学んで、
葬儀社様向けの経営コンサルに活かしたい・・・と、
ちょっと「いいところ」に行ってきました!

こちら、更衣室です!
富裕層向けホテルの会員制スポーツクラブと、同じような作りです・・・。
「ベルトコンベア式・産業系・健康診断」しか経験したことのない
人間にとって、初めての体験が始まりました。。。
2014年3月9日 10:17
夕日が沈むのを、じっくり観察したのは、何年ぶりかな??
いま、まさに暮れかけた夕日が、

地平線に沈むまでの時間は、
驚くほど、早いんですよねー。ものの2~3分。

夕日で思い出すのは、小学生のころ。
「夕日がどこに沈むのか、確かめに行こうぜ!」と、
自転車を必死に飛ばして、見知らぬ街まで、行ってしまったことがあります。
こんな経験、ありませんか?
そして、結局、追いつけず、
日が沈んだ後のまっ暗な夜道を、
友達と二人、不安で泣きそうな気持ちを抑えて、帰ってきた記憶。。。
ちょっと待て。。。
そんな感覚、、、最近もあったな~。
思い出した、新しい葬祭ホールの出店調査のときだ!!
出店の候補エリアが、絞れている場合の調査の必需品は、自転車。
走り回って、車では見つけられないような場所を、探し出すことができます。
腰痛に悩むオヤジが入手した武器が「電動自転車」
しかし、コイツが、くせもの!
軽ーく動いて、楽しいし、
行動範囲が広がるもんだから、
調子に乗って、どんどんどん遠くへ行って・・・・。
ただ、、、
電池が切れたときの重さと言ったら、ありゃしません!
重たいし、進まないし・・・。
体力が奪われてゆく、
なかなか良い物件は見つからない、
肉体と精神のダブルパンチ!!→ 日が暮れてくると、泣きそうになる・・・。
男は、いくつになっても、
やってること、あんまり変わらないんですね。
電動自転車には、気をつけてください。。。
2014年3月5日 8:43
「一流」を求めることをベースとしていますが、
「一番」を否定するものではありません。
葬儀社のコンサルティング先に、
「一番」となっていただくための経営支援こそ、
日本売上アップ研究所が、最も支持されているからです。
事実、「一番」には、お客様が集まります。
意図的に一番であることを作り、アピールすることが、業績アップの最短距離です。
「一流であり、一番」
最終的に、ここを目指すのは、当然のこと!
しかし、両方を同時に手に入れる・・・というのは、難しい。。。
順番として、
まず「一番」になりたいですか?
それとも、
まず「一流」になりたいですか?
この質問に対して、「まず一流になりたい」と答えた方は、
あまちゃんです!!
それなりの、恵まれた環境で育ったことに、感謝したほうが良いです(笑)
実は、技術貧乏になってしまうケースが多いのです。
最近、流行の「インターネット」の世界でも、
お客様を集めているのは、「一流」の会社ではありませんよね。
葬儀の「技術」のことを、
ほとんど知らない経営者が作ったサイトであったり、
葬祭業界に何の関係もないIT企業が作った「葬儀・サイト」が、
事実、お客様を集めています。
しかし、、、
「自分のことは、自分で見えないもの」です。
「一流」を目指すより、
まず「一番」を目指すべき、、、って、
クライアントにはアドバイスするのに、自分のこととなると、それができない。
「一流を目指す・・・」というコンサルタント。(笑)
医者の不養生とは、まさにこのこと。
第三者の目線や導きは、本当に必要ですね。
2014年3月2日 17:02

広島県からお越しいただいたお客様からいただきました!
感謝です。。。
もみじ饅頭ゆーたら「にしき堂」が、有名じゃろーけど、
地元じゃ、みんな「やまだ屋」を、買うんよ~。
広島のクライアントさんは、こんな注釈をつけて「やまだ屋」を、
誇らしげに、プレゼントしてくれます。
西日本を中心に、同様のことが起こります。
長崎県のご支援先は、
世間では「文明堂」のカステラが有名かもしれないけど、
実は、美味しいのは「福砂屋」のカステラさねー!!
ズッシリ感と、底のザラメが、ほんまもんのカステラったい!
と、教えてくれる。
北九州市の葬儀社様は、
東筑軒の「かしわめし」が本物です!
他のメーカーのは買わんように気をつけてください。
売店では、色々売られていますから!
とまで、教えてくれる。
「商品やサービス」が
「有名であること」と「優れていること」、、とは、一致するとは限らない。
前述のような「食品」を例にとれば、
「知名度」と「美味しいこと」は、別問題なのです。
「知名度」を、シェア・一番としたとき、
「優れていること」は、一流と言えます。
実は、コンサルタント業界も、同様なんです。
「セルフ・プロデュース」だけが上手な人は、たくさん存在しています。
それに、
「有名な会社」と「腕が良い」とは、完全に別問題。
「知名度な会社」に所属していたからこそ、その内実は、よくわかります。
本気のお客様は、「一流」を知り、選択する。
でも、大多数の本気じゃないお客様は、「一番」に、ムードで流される・・・。
もちろん、コンサルタントとしての我々は「一流」であることを自負しています。
「やまだ屋」「福砂屋」「東筑軒」と、同列に入りたい!!
「本当に費用対効果が高くて、
売上が上がるのは、日本売上アップ研究所のコンサルティングだよ!」と、おっしゃっていただいている
口コミと評判を、もっと大切にしてゆきたいと思います。
2014年2月27日 9:45
ソチ・オリンピック、楽しかったです。
レジェンド・41歳の葛西選手から、
15歳のスノーボーダーまで、メダル獲得の年齢差は、実に36歳。
メダル獲得の「種目数」も、過去最多とのこと。
この広がり=「多様性」は、
日本が成熟した国であることを示す、ひとつの証なのかもしれません。
後進国ほど、メダルを取りに行く競技を絞って、国策的に育成します。
(これは、マーケティングでも同じですね!)
メダルはなくても、「記憶の金メダル」は、真央ちゃんの涙。
筋書きのないドラマだから、スポーツ観戦は、やめられません。
そして、
ビジネスマンの胸に突き刺さるのは、
スノーボードの竹内智香選手ではないでしょうか?
強くなるために、スイスの代表合宿の門を叩いて、開かせ、
外国人として、たった一人で参加。
ビジネスの世界なら
ライバル会社に「ノウハウを学びたいから、働かせてくれ」と言って、
実際に入社させてもらうようなもの。
資金を集めるために、奔走し、広島県の観光大使をつとめ、
オリジナルのボード開発にも、関わる・・・。
思いを行動に移すパワーや、
経済的な自立を目指す姿勢に、学ぶべきことが、本当に多いと思います。
パイオニア(=開拓者)精神にあふれ、
「野武士のようなたくましさ」の匂いに、共感してしまうのです。
「全力プレイ」をしていると、周りは応援したくなるな。
「依存を求めず、自分の足で立つ姿」は、やっぱり美しいな。
そんなことを、思いました。
どうでもいい「思ったこと」話・・・<番外編>!
・スキーのジャンプ
飛行した後、U字型の観客席みたいなところで、スザザザザッーーと、
カーブしながら、止まる瞬間。 これが一番、カッコイイと思います。
・フィギュア・スケートの「ショートプログラム」・・・
ショート?? 案外、時間が長いなー。
(まだ、この選手、終わってないの??)と、何回も思いました。
・フィギュアの解説者・・・「トリプルルッツ」・「ダブルループ」・「ダブルトウループ」・・・
「跳んだ時だけ、しゃべる」というのが、業界の掟なのかな?
技を見極めるのが、スゴイことなのかな??いつも、よくわからんなー。
2014年2月22日 21:32
ブログをスタートする際に・・
ノウハウの核心部分は、書かないブログにします。。
「完成品」は、公開しません。
「材料」や「工具」「工法の発想」を、公開します。
と、宣言しましたが・・・。
このくらいなら、公開してもいいかな・・・ということで、
特別に!
あるご支援先での「親族控室リニューアル」の打ち合わせ風景です。
ホール見学者が、入室した瞬間。
「え!?本当に、ここに泊まれるんですか??」という声を上げる
リニューアル・ポイントが、満載です。

貼り分けクロスのカラーリング原則。
床の間に仕掛けた、間接照明。
床の間の調度品は、伝統にとらわれないモダンなものを。

窓や、障子の形状は、規格サイズでないものを。
窓ごしの風景は、100万円の絵画に勝る!
ヘリなし畳よりも、安く上がる和風床材。。。等々。
ローコストで、
古いホールや控室を、センスあふれる家族葬専用のものにリニューアルさせると、
業績アップに、もの凄く貢献してくれます。
2014年2月18日 8:48
バレンタイン、
ありがとうございました!!

こんなに愛らしい子たち・・・
とても、とても、食べれません!!! 😥
まあ、でも・・・
結局、こうなるんだけどね!

ガブリ!
肉食系男子、万歳!
ワーッハッハー 😎
2014年2月15日 6:50
先日の「25周年」記事の第二弾。。
この式典の列席者は、さすが・・・の一言。
業界内外の著名な方ばかり。
やはり、成功者の原則。。。
社外で交わりのあるメンバーの質が、違いますネ!
感心しているのも、束の間、
「逃げ出したい」時間が、やってきます。
。。。。「祝辞」
あー、もう本当に、ダメなんです。
しかも、このキラキラまばゆいばかりの列席者の前で。。。しかも、2番目。
「コンサルタントなんだから、慣れてるでしょ?」
良く言われますけど、、、実は、全然、質が違うものなのです。
当社のセミナー・勉強会は、「事実」を伝えることをメインにしたもの。
「こうゆう葬儀会社があって、数字がこうなりました ~数字で紹介」
「取り組み事項として、実行したことは、これです ~映像で紹介」
「実行のためのポイントと原則は、これです ~図表で紹介」
現場で、実務的に、売上アップに関わってきた事実を、
正確に伝えることができれば、基本的には、それで良いのです。
笑わせる、あおる、感動させる、、、は、
当社の場合には、副次的産物の域を出ないので、祝辞とは、ちょっと違うものなのです。
「笑わせ、あおり、感動させる」を、
メインに活動しているコンサルタントは、きっと祝辞が得意だと思います。
生きた心地のしない祝辞、、、
なんとか「お役目」を果たすことができました。

売上アップ・コンサルタントとして、
これから社長さんが、スムーズに経営できるよう、
スタッフさん向けのネタを、軽く仕込みながら。
祝辞は、どんな経営セミナーで話すよりも、緊張します。
このチャンスを与えてくれた社長さんには、とても感謝です!
が、今後、
本当に、祝辞だけは、ご容赦願いたい!
何でもしますので!
2014年2月13日 9:45
クライアント先の25周年式典に、ご招待していただきました。

「熱き思い」が、成長の原動力となり、
「感謝の心」が、成長の推進力となる。。。そんなことを再認識しました。
・修業先でのくやしい思い。
・近隣住民との確執。
・大手企業の横暴。。。
逆境をバネにして、壁を打ち破り、
質的変化を重ね、
今の会社を手塩にかけて育て上げ、25年目。
「なにくそ!負けるものか!!」という熱き魂の青年が、
「ありがとう」「おかげさまで」も言える器の大きな男になっていった歴史。
熱く優しい男と家族、スタッフ達の物語は、
これから50年、100年続いてゆくことでしょう。
中小企業の経営者には、
こうゆう要素が、多分に、土台として必要不可欠なんだと思います。
コンサルタントという職業柄、
ふと、ご支援先の社長達を、思い返す。。。
2つの要素、、、持ち合わせていないな・・・。
あるかもしれないけど、薄いな・・・。という社長様は、
こうしてみて欲しい!!
1)この事実を受け入れ、自分で認識すること。
2)「こうしたいなあ・・・」という夢はイメージし、周囲に伝えること。
3)ビジネスで「付き合う相手」「交流する人」を、
中小企業魂があふれている、伸びている人を中心としたものにすること。
2014年2月7日 23:55

クライアント先にご訪問して、
いつも座る席に、こんなもの・・・。
栄養ドリンクだ。。
幹部スタッフさんが、ご用意してくれていたものでした。
疲れ気味なの、、、
ばれているみたい(笑)
おかげさまで、
全国各地を飛び回り、たくさんの仕掛けを行い、
とても忙しい。。。
ありがとうございます。
もう大丈夫です!!
ビンビンの興奮コンサルタントです!
一番の活力剤は、
毎月の実績表が、プラスで推移していること。
着実に前進していることが、実感できること・・・なんです。
2014年2月3日 9:50
春に向けた販促の打ち合わせで、
「ダイレクトメールは、1枚当たり経費が高いので、
このタイプの工夫した仕掛けで・・・」と、
定番の提案した私に、ご支援先の社長が、かけてくれた言葉。
「中西さんが、ここまで真剣に、DM企画を練っているなら、
高くなってしまうタイプのDMを作っても、いいんじゃないですか?」
「僕は、売上アップこそが最大のコストダウンだと思っていますから」
確かに。。
いつの間にか、コンサルタントである私自身が
「ダイレクトメールとは、こうゆうものだ」という固定概念にとらわれていました。
リニューアルの経費にしろ、
チラシ、DM経費にしろ、研修の費用にしろ、人件費にしろ、
コストダウンを考えるのは、当然の如く、良いことです。
しかし、
コスト以上に売上を上げることができるならば、、、
つまり、売上に対する費用の「比率」が下がるほどに、
実績を上げることができるならば、、、
最大のコストダウン策は、売上アップに違いありません。
経費を圧縮するとき、
お客様の目に見える部分のコストを、削ってはいけません。
コストカットは、お客様の目に見えない部分(バックヤードや事務所)から、手をつけるのが、定石です。
万全の準備で、企画立案した作戦を実行するために、
大事なお金を投入してくれる社長の期待に応えなければなりません。
また、営業の皆さん、ホールスタッフの皆さんにも、
これほどの度量で、販促費を使ってもらえることのありがたさを伝え、
現場での戦術実行度を100%以上にしてもらわなければなりません。
最新の武器を、潤沢に与えてもらったのはいいけれども、
兵士が弱い・・・では、勝てる戦も、負け戦になってしまいます。
春に向けて、売上アップを果たすための準備が、
全国各地で、着々とすすんでいます。
2014年2月1日 8:54
長野のクライアント様へお伺いする道中。。。
10年もの間、お世話になっている会社さん。
毎年、堅実に実績を上げてこられ、
社長も、幹部さんも、スタッフさんも、明るく、前向き、そして美しい!!ので、
お邪魔させていただくのが、楽しみです。

名古屋~長野の特急電車からの車窓、、ここが一番の絶景スポットです。
雪の下で、草花の芽が、
静かに、でも力強く、春を待つ準備をしている。
遠くに川中島を望みながら、思います。
苦しいこと、大変な時期は、
長くは続かない。その先に、春は必ずやってくる!
日本の四季のように。
つらい時期があるからこそ、
実りの時期を、感じることができる。
逆に言えば、
楽しいことばかりでは、楽しさを感じることはできない。
苦しいことがあるからこそ、楽しいことを味わえる!!
準備の大切さ、試練への感謝。
この風景を見ながら、胸にしみます。
でも、
春は、早くやってくるに越したことありませんよね!
2014年1月26日 8:45

ご支援先の葬祭会館の屋根に、つらら。
青空とのコントラストが、とてもキレイです。
そして、館内には、薪ストーブ。
ぱちぱちと心地よい音を、響かせながら。

じーっと火を見ていると、なぜか、心が落ち着きます。
原始時代からのDNAでしょうか?
火を使用することは、人類の最大の特徴です。
人間以外の生物は、火を怖がります。
恐ろしい、でも近づいてみたいという好奇心。
ここから、人類は発展したのだろうな。。
猛獣から身を守り、
料理に使い、灯りをとり、暖をとり、
エネルギーに変えて、文明を発展させてきました。
理屈じゃなく、自然に反応してしまうDNA。
人の本能や、五感を刺激する演出・・・
葬祭業界でも、積極的に活用してゆくといいでしょうね!
2014年1月21日 21:38
今から20年前、
大学を卒業して、船井総合研究所に入社したときの出来事です。
全社の新年会を兼ねた内定者研修で、
総務の取締役が、私たちに課題を出しました。
「新年会の立食懇親会で、船井総研の社員に挨拶し、たくさんの名刺をもらってきなさい」
「集めた数を、後ほど発表してもらいます」
きっと22歳の当時から、偏屈者だったのでしょう。
「コンサルタントになりたい者に、これって必要なのか?何の意味があるんだ?」と。
でも一方で、同期の仲間たちには負けたくないという面もあり、、、
一計を案じました。
よし!
船井幸雄会長の名刺だけをもらおう!
たぶん、誰も会長には、近づかないだろう。
そして「僕は、この1枚です」と、あの役員に出してやろう・・・。
「名刺をください!」
勇気を出して、船井幸雄会長の席に近づき、こうお願いしました。
ニコニコと、あの笑顔で
こんな生意気な若者に、丁寧に、名刺を渡してくれました。
どんな人にも変わらぬ対応で。
そのとき、何を話したか、まったく覚えていません。
優しい人だなあ・・・と、思いながらも、
目の鋭い輝きに「百戦錬磨」を感じさせる威圧感があったことを
鮮明に覚えています。
ほぼ100%、船井会長は、私の名前すら覚えてはおられないことでしょう。
雲の上の存在とは、まさにこのこと。
500名以上在籍するの社員の一人として、
月に一度の講話を聞くくらいの関係しかありませんでした。
入社2年目の6月の蒸し暑い朝、、、
徹夜の仕事明けで、会社のトイレの洗面台に水を入れて、
頭を洗っていると、ふいに船井会長が、入ってきたことがあります。
びっくりした表情で一見して、
「おつかれさん」
と、声をかけていただき、隣で、淡々と用を足しておられました。
個人的に接触したのは、この2回きりです。
あとは、たまにエレベーターで一緒になって、嬉しい気持ちになることくらい。
席に戻ったら、即、自慢です。
「おい!さっき、エレベーターで会長と一緒になったぞ!、
どうや、俺からも、ついてるオーラが出てるやろ~」と。
1月19日、
船井総研の創業者である、船井幸雄氏が、
永久の眠りにつかれました。
今の自分の土台となるものを作っていただいたことに、
感謝してもしきれません。
今でも、理想とするコンサル会社としての在り方は、
諸先輩方の話に聞き、
私が入社当時には、まだまだ、その空気感が色濃く残っていた、創業当時の船井総研。
予算なんて、ない。青天井。
好きなだけ働いて、好きなだけ給料を稼げばいい。自分で給料は決めるもの。
ルールは作らないほうがいい。管理もしないほうがいい。
「ケンカの船井」と評判がたつほど、競争にめっぽう強い。
「船井が味方についたらしい」との情報だけで、クライアントのライバル会社は、恐れていた。
一芸に秀でた個性あふれるコンサルタントが
バリバリ仕事をして、クライアントの業績を上げる。自立したプロの集団。。。
ちなみに、船井総合研究所とは、後から変更したもの。
船井幸雄会長が、創業したときは「日本マーケティングセンター」という社名でした。
法務局に登記のために出向いた社員に、電話で指示しながら、決めたそうです。
「わかりやすくて、大きな名前が良い」と。
3年前に創業した当社「日本売上アップ研究所」という社名は、
そんなところにも、影響を受けています。
師と呼ぶには、あまりにも遠い存在。
しかし、その御恩に報いるためには、コンサルタントとして
ひたすらに進むべき道を歩み、果たすべき役割を果たすことしかありません。
青く凛とした冬の空を見上げ、感謝の念とともに、そう心に誓います。
ありがとうございました。