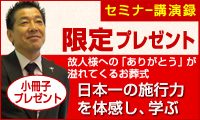2017年4月2日 8:46

春は、別れと出会いの季節・・・。
今回は、ご支援先の社長が、SNSに投稿されたコラムを、そのまま転記します。
↓↓↓
コラムを読んでくださりありがとうございます。
「お別れの時、去る時」というのは、「人の本性が一番現れる時」と言われているそうです。
これを聞くと、どのように人の目にうつるのか怖い!
という人もいますよね・・・きっと。
先日、当社の優秀な社員、●●さんが結婚退職、遠くに引っ越されるので、送別会を行ってきました。
●●さんの本性は・・・誠実な印象そのまま、でした。
彼女は、前面に出る方ではありませんが、「縁の下の力持ち」タイプ。
チームワークを大切にして、しんどいときでも、笑顔で誠実に対応されていたので、
上司・同僚・部下からとても頼りにされていました。
また退職の際にも事前に上司と相談しながら、
慎重に話をすすめられ、ぎりぎりまでお店のことを気遣っておられたようです。
信頼感、存在感の大きさというのは、
接する期間の長い、短いだけではなく、その人のあり方、姿勢によって大きく変わるものだなあ、
と改めて彼女から学ばせてもらいました。
●●さん、大阪でも●●さんらしくがんばってください!
戦友として一生、応援していますよw
もちろん、●●さんが抜けたあとのお店も、
見えないところ、見えるところで精一杯応援します!
↑↑↑
自分は、去る時、どうだっただろう??
転職は、一度きりだけれども、、
前職の先輩も、後輩も、同僚も、時々、飲みに行こう!と声をかけてくれるし、
いつでも、こちらから声をかけることもできる。
当時の社長や、取締役にも、当社でご講演いただける間柄ですし、、。
私の本性は・・・まあ平均点くらいかな?
2017年3月28日 7:31
先日のブログの続き。
ご支援先の式典には、
女子ソフトボール・日本代表元監督。宇津木妙子さんが
ゲスト講演に来られていました。
この講演会を聞きながら、
書き留めたメモを、転記しておきます。
・「負けず嫌い」が、自分を成長させてくれた。
小学生のとき、先生との個人面談を終えた親から
「アンタが、恥ずかしい」と言われ、奮起した。皆さん自身はどうか?皆さんの子供は?
・「自分の得意分野で一番になる。」と決めてから、道が拓けた。
足だけは速かったから、足を活かして、塁に出ること。
声を出すことは、誰にでもできるから、大きな声をたくさん出すこと。
・企業チームは、強いだけでは成立しない。
地域に「愛されるチーム」にならないと、生きてゆけない。
挨拶をする、子供たちに教える、清掃活動をする・・・。
・毎日、選手と挨拶をすること。
スタッフの感情が、わかるようになってくる。
・監督として赴任後、早く選手を把握するためには、個人カードを作る。
家族構成や、中学・高校の球歴、得意・不得意、性格、技術。
・監督時代、シドニーオリンピックでの逆転負け。
「レフトのエラーで敗北した」という宇津木さんの発言に対して、
選手たちが反論「あれは、みんなのエラーです!」→その瞬間が「チーム」となった瞬間。
・組織に属する者は、その「組織の目的=勝つこと」のために、
どうすれば良いか考え続け、その方向に行動すること。
仲間内の愚痴だけでは、何も生まない。意味がない。
納得できないことは、先輩にも言うし、監督にも言うべきことは、言ってきた。
組織のために、自分が果たすべきことをやっていれば、何でも言える。
「やっていない」者ほど、愚痴になる、正面から言えない。
・意見が対立するときには、
根気よく意見を言い合い、やることをひとつ決める。
2017年3月26日 7:19
クライアント様の
周年式典に、ご招待いただきました。
知り合ってから、もう17年のお付き合いとなります。
売上規模は、当時から比べれば、5倍以上に伸び、
一緒に学んできた勉強会の仲間の会社も、成長した姿で、一堂に会しました。

「拠るべきノウハウや、原理原則」と
「共に学ぶ仲間」の質によって、人生は決まる。。と実感します。
「技術系」に行くのか、
「売上系」に行くのか「利益系」に行くのか、
はたまた「ゴルフ系?」「家庭サービス系?」「組合系?」
それを選択するのは、すべて自分自身です。
追記・・・
思えば、成長した会社の経営者様は、みんな
経営の実権を把握するのが、譲ってもらうのが、早かった。
こちらのご支援先では、お母さまが、長く経営に携わっておられ、
時折、「〇〇(社長のお名前)!!」と、
ケンカ腰(に聞こえる口調)で、経営実務について、異論を唱えていたけれど、
その場の、それ以上は、何も言わなかった。
「そうかい!じゃ、アンタの好きにしな!」
そして、何事もなかったように、普通の日常に戻る。
息子である社長も、激しく反論しながらも、
それを受け止めて、なんとなく、経営に反映させていた。
コンサルティングの最中、2回に1回は目にする、この光景。。
私の中では、この会社の「名物」の風景です。
近くで見ていて(お母さまも、息子さんも、えらいなあ・・・)と、
ずーっと思っていました。
2017年3月23日 23:13
苦手な食べ物・・・
好んで食べないもの。その名は「トマト」。
しかし、このように多種類を並べられると、
つい食べてみても良いかな??なんて思う。

あらゆる商品には「アイテム・パワー」理論が、適用されます。
同一カテゴリーの商品が、複数アイテム集まると、
魅力ある「商品群」に見える。
これが「アイテム・パワー」です。
たとえば、
手ぬぐいが1枚だけ置いてあっても、なんてことないけれども、
ズラリと、いろんな柄が展示されていると、つい足を止めて、買ってしまう。
ご支援先の例で言えば・・・
「ミニ畳」も同じ。
色んなカラーや、縁(ヘリ)のデザインが並んでいてこそ、売れる。
1枚だけ「ミニ畳」を置いても、なんの変哲もない。
食事の際に出される「おしぼり」の使い終わった後の姿さえ、
すべて、写真に撮って、並べて展示してみれば、「芸術」になる可能性もある。
「アイテム・パワー」の威力で、
トマトを食べてしまいました。
※
トマトの味は、好きなのです。
トマトソース、大好物です。
食感が・・・苦手でして。。
きっと「あるもの」を食べたときの食感と、まったく同じなのです。
その「あるもの」とは・・・!?
ご興味のある方は、お会いした時にでも、聞いてくださいませ。
以降、トマトを食べることができなくなるかも、しれません・笑
2017年3月18日 7:41
クライアント葬儀社様からの帰り道。。
こんな風景を目にしながら、、、

クライアント様の売上が上がり、順調なら、
ただただ、嬉しく、
良い方向に進んでいれば、希望が膨らむ。道筋が見える。
「ヨーシ、あの光に向かっているぞー!」
逆に、クライアント先に問題点が多いなら、自分の力不足を嘆き、
打開する方法を、必死で見つける。考える。
「ナニクソッ、あの光を絶対、つかんでやる!!」
たぶん、
お付き合い先の経営者と同等か、それ以上に、
その会社の経営のことに、真剣です。
そうでなければ、
コンサルタントなんて仕事は、やっていけないのです。
2017年3月11日 21:03
最近、忙しさを理由に、
お役に立たない不真面目な内容が目に余る、このブログ・・・。
「週に2回の更新」を、スタッフちゃんに、約束したからには、
内容が薄くなったとしても、なんとか守ってゆきたい。。ので、
何とぞ、ご容赦くださいませ。
忙しい分、
たくさんの「ネタ」は、メモ書きレベルで、たまっています。
今日は、お役に立つ内容だと思います。
ご支援先といつも食事に行く「とんかつ屋さん」でのワンショット

席を片づけ中、
テーブル・ボックス席を掃除するときには。
毎回、全スタッフが、テーブルの下に「体ごと」潜り込んで、拭き掃除をしています。
ホールの場合も、飲食店の場合も、どんな業種でも「掃除」の基準は、難しい。
でも、
「テーブルの下を掃除する」というルールでなく、
「テーブルの下に潜り込む」という基準を作れば、誰でもできる。
やったか、やっていないか、誰でも、判断できる。
実際、きれいになるし、
この行動を行うことで、心が変わる。
「お客様のための店をキレイに」と、言葉で言うよりも、
この行動が、そうゆう心を作る。一事が万事に通ずるのです。
わかりやすい「基準」を作って、
指示を出しているのに、
無視して、やらないヤツがいる場合は、どうする??
ふ~~、プハッーー。
2017年3月9日 21:21

スケジュール、パンパンの状態のこんなときに、予定外の仕事が飛び込んできて、
急きょ、空港に併設されたホテル泊まって、ご依頼に応えることに。
明日は、朝イチで飛びます!
チケットカウンターは、緊張しますね!笑
後ろから、ガバッ!とVXガスやられたらどうしよう!
目の前で、一人の女性が気をひいて・・・とかされたら、
一発で、策にはまること、間違いないもんなー。。。
・・・
笑っているアナタも、きっと同じですよーー!
2017年3月5日 22:51

当社のメインバンク。。。
といっても、振込先であるだけなんだけど・・・。
本店へ!
強盗する気にもならないほど、どかーん!としている。
この建物の「窓ガラス1枚分」ほども、
この銀行を儲けさせていないから、特に、歓待もされず(笑)
警備員が、ジローっと、こっちを向いてました!
そういえば、、、
大先輩のコンサルタントの、こんな言葉を思い出しました。。
100年続く一流企業を作るなら「憧れの本店」を作れ。と。
2017年3月2日 8:31

怒涛の如く、仕事が入ってくる日々。。。
ふとした風景が、心の癒し♪♪
月と金星が、大阪の空に。。
アタマに流れるのは、このメロディ。
「金星と、冥王星と、月と太陽と~♪」
「嗚呼、君の心に~、僕は住んでいますか~♪」
F1ドライバー・中島悟さんを起用したエプソンのCM。
かっこよかったなあ・・・。
フルコーラス版は、こちら。
2017年2月26日 22:46
皆様のおかげで、、、
個人的に「経済的な余裕」が出てきたこと(笑)
それに、仕事で身にしみ込んだ「探求心」のせいで・・・。
同じ商品のグレード違いは、
同時に買ってみて「スプリットラン」して、確かめます!

「発酵タイプのバターのほうが高額だけれど・・・価格の分だけ味が違うのかな?」
「市販のヤクルトと宅配のヤクルトの、シロタ株の効果の違いはあるのかな?」
「ヤクルトLGは、甘さ控えめらしい・・・どれほど味が違うのかな?」
ほんとに、小さな余裕ですが・・・。
自分としては、大きな進歩。
「迷うなら、疑問に思うなら・・・両方、買ってみよう!」と、
躊躇なく言えるようになった・・・(単価1000円以下のものならば)笑
ヤクルトは、今年の花粉症対策です!
「乳酸菌」が効くとのことで。
頼んだぞ、1本・400億個の「乳酸菌シロタ株」!
全部で14本あるから・・・10日で、5600億個、生きたまま腸に届けるからなー!
これでダメだったら、渡辺謙を信じない!
花粉症対策には、注射、漢方、てん茶、花粉エキス・・・・等々
毎年「スプリットラン」風に、試してきましたが、
効果のほどが、良くわからない。
「やらないよりは、良かった気がする・・・」
「でも、まったくやらなかった時との比較ができないからなー」
実は・・・一般的なコンサルティング会社も、そうなりがちな存在なのです。
「花粉症対策」みたいなコンサルタントとは、
しっかり一線を画した経営支援をしてゆかなければ・・。
花粉症の季節が来るたびに、そう思います。
右の鼻腔だけ、とか、左の眼だけ、、、とか、花粉症対策、やってみたいなー。
一般の企業にとって、スプリットランとは、
これと同じくらい思い切りのいる、大変なことなんです。
2017年2月25日 22:36
スプリットラン(Split Run) 別名:ABテスト
2つ以上の広告を同時に出して、
どちらの広告が、効果が高いのか?ということを比較・検証すること。
日本語で言えば、「効果比較を前提として分割した広告」といったところでしょうか。
マーケティング用語です。
「こんな販促方法が良い!」とか
「このホールが良い!」と発表しても、
実際、まったく同じ条件=同じ商圏、同じタイミング、同じターゲット等々・・・
に対して実行した結果とセットで、話している人は、ほぼ皆無。
ある一現象だけを、「それが、すべて」のように話す人が。大多数。
ビフォー・アフターの数字が明確になれば、まだ良いほうでしょう。
実際「同一条件下での比較」を数字で示すことは、なかなか難しいものです。
大きな問題点が3つほどあります。
わざわざ2つの広告を作るという労力の問題。
それに、余分にかかるコストの問題。
広告効果が出なかった側の売上ダウンのリスクの問題。。。
つまりは「経済面での余裕」と「心の余裕と探求心」がないと、
葬儀社が「スプリットラン」を実行することは、難しいのです。
WEBの世界ならば、比較的「労力」だけでできるので、頻繁に実施可能です。
「広告の文章を変えてみる」とか「バナーを変更してみる」等々、実施してみて、
その違いを、反応を数字で確かめます。
WEB業界は「スプリットラン」が実行しやすい業界です。
しかしながら、
最近では、おかげさまで、少し余裕のある葬儀社のご支援先も増えてきました。
お互いの努力の成果です(笑)
「チラシの色は、実際、何色が良いのか?」
「割引設定による効果の違いは、どれくらいあるのか?」
「相談会やイベントの本当の成果はどうなるのか?」
「控室をリニューアルしただけで、売上は上がるのか?」
こんな「スプリットラン」を、実行しています。
我々とお付き合いいただき、
売上が上がり、余裕のできた葬儀社が、スプリットランを実行し、数字を検証した
本当に効果のある売上アップ法を入手できることは、とてもお得です!
2017年2月19日 21:08

勉強会のお昼ごはんに行った和食屋さん。
すでに、桜の飾りつけ!
ステキですね。
以前も、ブログに書きましたが、
「繁盛店の季節感は、前倒し」
コンサルタント風に、小粋に言うと・・・
「季節の語り部」たれ
葬儀社と花=季節感は、縁の深い存在。
ロビーや、控室、祭壇づくりの参考に!
2017年2月15日 9:07
今月のANAの音楽プログラム。
「ウエディンベル」に「サムデイ」「卒業」「クライオン・ユアスマイル」・・・
GOOD!

今月は、ANAだけでも5回は、搭乗することになるから、
楽しみが増えました♪♪
機内では、時間に余裕のあるときには、
プログラムの「落語、全日空寄席」を聴いて、話術・古典・人情?等々の勉強をしています。
月に1度の定期訪問先が多いので、
2月は、忙しい。営業日数が28日しかないから、物理的にこなしきれなくなるのです。
機内でもパソコンやノートを開いて、仕事をしないと、間に合わない。
そんなとき「落語」は、頭に入ってこない。
なじみのある音楽が、モチベーションを上げてくれます。
新幹線移動のときには、、メールへの返信ができるから、ちょっと便利。
返信内容が、即・売上アップにつながる案件が多数なので、真剣に考えて返信する。
1本の返信に、10~15分はかかる。
1日10本に返信したとすれば、、合計で100分~150分!2~3時間の仕事。
これが、1日20本とか、なっていると、もはや、半日仕事。
じっくり考えているうちに、送信を忘れていたり、
後回しで良いものはそのままになっていたり
・・・と、大変申し訳ないことも、多数あるのです。
特に、特に、
社内のメールは、お客様優先で対応しているので、
どうしても、後回しになりがちで・・・申し訳ない。。
新幹線がトンネルの中に入って、電波が悪くなり、返信できなくなると、
その間に、携帯に入っていたライン等への、返信をはじめる。
そして、トンネルを抜けると、また、パソコンに戻る・・・。
3月末ごろまでは、そんな日々。
岡山~広島・山口は、トンネルの連続で、日本一仕事ができない路線。
。。イライラするから要注意。
で、
こんな時期に、当事務所からアベックで新婚旅行に行くヤツらがいる・・・(アベック~~!)
「連絡、つきますから!」って、言ってたから
いっぱい、ハワイに仕事の連絡したるねん(笑)!
2017年2月12日 20:57

完成に向けて、建築中の新店舗!
これまでのノウハウの粋を結集したものを、作っています。
予算が・・・ややオーバー気味ですが・・・。
それでも相当、安く上がっている。
坪あたり60万円。。看板は別で。
おそらく5年で回収の、投資対効果・抜群の出店フォーマット。
さらに、忙しくなりそうです!
2017年2月10日 21:22
クライアント先の「年度方針発表会」で、いただいた表彰状。。

表彰状を、
人生で初めてもらったのは、小学5年生のとき。良く覚えている。
写生コンクールで、加古川市の銀賞か銅賞か・・・を、もらった。
(牛の絵だったなあ~。今思うと、肉牛だな。)
「自分は、ダメなほうの人間だ・・・」と思っていた内気な中西少年に
「あ、、意外と、俺もやれるのかも!」という「自信」のかけらを芽生えさせてくれた。
大人になってから・・・ほとんど表彰されたことってない人生。
船井総研に勤めていたころには、
毎年、表彰の対象になるキャンペーン的なもの(何かを売れ!的な・・・)は存在していたけれども、
斜に構えて、お付き合い程度に、こなしていた「不良社員」。
「ご支援先の業績を上げるコンサル力や、生み出したノウハウの質を評価するキャンペーンがあるなら、
優勝目指して本気でやるけど、営業マンとか、販売員みたいなキャンペーンには、俺、参加しないよ~!」
な~んて。
仕事の本質を追求しすぎる??とっても嫌なヤツだったわけです。
実力がなくなると、すぐに切られるタイプですね。。
本気を出して、たまに1位をとることもあった。
それは、キャンペーンについて、
会社や上司に対して「クソっ!コイツ・・・腹立つ!」ってことがあったとき。
その理由は・・・・
表彰と同時に、壇上で何か話させてくれるから。
そのとき「全員の前で、思いっきりイヤミなこと、言ってやろう・・・」という不純な動機で(笑)
でも、そんなときに限って、インタビューなし・・・。
不純な動機、察知されていたのか、
神様が「それを言うと、ダメだよ」と、導いてくれたのか、、
今回の表彰状は、
子供のころのように「ただ、ただ、嬉しい・・」感謝です。
いつも打ち合わせさせていただいている皆さんの顔が、思う浮かびます。
わざとらしーく、誰かの目につくところに、置いとこう。。笑
2017年2月4日 11:48
クライアント先のお近くのスーパー。。。
このPOPを見ただけで、
「繁盛店」であることがわかります。

特殊なPOP技を駆使するわけでもなく、
特別な仕入れルートなわけでもなく、
誰にでもできる工夫で「できることをやっている」というところに、さらに好感が持てます。
是非、応用して参考に。。
2017年1月29日 21:47
先日のブログと関係ある、グレーな本音。
実は、、、
コンサルのご依頼があっても、半分くらい、断っています。
その理由は、
当社の既存のコンサルティング先葬儀社様と
商圏が重なる地域の葬儀社様からのご依頼だからです。
当社の契約先は、1商圏で1社。
でないと、マーケティング上、競合してしまいます、
日本には、まだだ当社が支援に入っていない地域が、たくさんあるのに・・・。
なぜ、、、、
支援に入ることができない葬儀社さんからのご依頼、お問い合わせが多いのか!?
それは、きっとこんな理由だろうと思います。
契約した場合、その地域の施行シェアを、確実上げてゆく方法を提案しますから、
クライアント葬儀社様が、それを忠実に実行していただいていると、目に見えて、変化があるわけです。
「ライバル店のチラシの雰囲気が、良くなった」
「ホールづくりが、洗練されてきた」
「やることにキレが増し、しつこく食い下がってくる」
「手強い存在になってきた」
・・・・・そして最終的には。
「自社の売上が落ちてきた・・・・」
どの段階で、当社に「依頼をしよう」と決断をされるかは、その会社の経営者の感度次第。
もっとも、どの段階で依頼されても、すでにライバル店と契約している場合には、
お応えすることは、できないのですが。
地域でトップ3社に残っておきたい。
自分の商圏を守っておきたい。。
ライバルの会社が当社と契約してしまい、上記のような状態にならないためにも、
早めにお声かけいただければ・・と思います。
2017年1月27日 21:55
消費税8%導入が閣議決定された3年前、こんなレポートを配信していました。
「ひとつの業種で、地域にトップ3社しか残れない時代となる」
「中小企業は、トップ3に入るか、入らないかを、今、決めなければならない」

2016年の秋、ファミリーマートとサークルKサンクスの統合が発表され、
順次「ファミリーマート」看板に統一されています。
コンビニ業界は「セブンイレブン」「ローソン」「ファミリーマート」のトップ3社体制となりました。
ビール業界では、アサヒとキリンという2大勢力が、一部地域の配送面で提携することになり、
自動車業界では、トヨタ自動車とスズキ自動車が、業務提携を発表しています。
日産自動車が、三菱自動車を傘下に収めていますので、
「トヨタ」「日産」「ホンダ」の3グループ体制への序章とも言えます。
葬祭業界にも、やや遅れながら、
この流れは、確実にやってきています。
・・・・5~6番手の葬儀社が、今さら動いても、もう遅い??・・・・
せめて、消費増税が決まった時点から、動いていれば。。。
いや、葬祭業界は、やや遅れた業界。
地域によっては、まだ今から動いても大丈夫な地域もある!
挽回可能かな??
リニューアルの費用と、コンサルティング費用を出せる、、
その余裕のあるうちに、ご相談くださいませ。
2017年1月22日 19:05

繁盛ラーメン店の、ティッシュペーパー。。
カウンター下から、こうして出ています。
ステキです!
机上の空論ではない、実戦で鍛えられ人からしか出てこない発案です。
まさに、現代の「城」づくり。
裏から見ると、このようになっています。

2017年1月20日 21:02

社会人になって、2年間は、死ぬほど仕事をした。
会社には、寝袋があり、週のうち1~2日は、終電にも間に合わず「泊まり込み」での仕事。
色んな先輩からもらう「圧倒的大量」の仕事を、納期までに仕上げる。
「仕事を断ってはいけない」という暗黙の了解。。。
もし断ったら「アイツ、断ったらしい・・・」という事実は、先輩方全員の知るところとなり、
仕事は、一切まわってこなくなる。
さすがに土日は、昼前くらいに出社すればいい。
クライアントへの調査・提案結果をまとめた資料を提出する「報告会」前でなければ、
土日は、21時とか22時には帰社できた。警備員のオッチャンとは、めちゃめちゃ仲良しになった。
同じ部署の先輩は、優しかったので、
2週間に1回くらいは、完全に休める日がある。
そんな休みの日には、ここぞとばかり、昼まで寝て、
昼前に起き出して、この喫茶店に出かけていって、新聞や雑誌を読んで、まったりする。。。
家にいると、電話がかかってきて呼び出されるので、外に出ておいたほうが安全!
これが「隠れ家カフェ」好きの原点。。
自分のもとに、クライアントから依頼が来るようになって、
スケジュールが半分以上、つまり週に3日くらい埋まってくると、
先輩からの仕事を、選んで断れる雰囲気が出てくる。
そうなってきたのが、3~4年目。
土曜か日曜には、この喫茶店に出かけて行って、
新聞を読んだあと、自分のクライアントさんのための仕事をするようになった。
そのレトロ喫茶店、
立ち退きのため、閉店に。。。
たぶん最後になるであろうこの雰囲気を、初心を思い出しながら、懐かしむ。