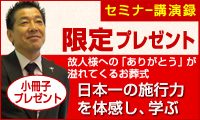2017年6月16日 21:17
本日は、東京に宿泊。
ゴジラが名物の「新宿・東宝ビル」を望む。。

写真右上に、ゴジラのアタマが、見えています!
これを見て、どんなことを思う??
「ゴジラ、かっこいい!」
「近くで見たいー」
「誰が、考えたのかな?」
「どのくらいの費用がかかったのかな?」
それぞれ、色んな感想があると思います。
現時点の私が思ったことは・・・
「これは、ゴジラ本体よりも、建物に写るゴジラの影が、かっこいいなー」
「これも、計算して作ったんだろうなー」
「ん??スクリーン代わりになっているのは、マンションに見えるけど・・・住民からクレームは出ないのかな?」
「どうやって話をつけたんだろ?」
そんなこと。
職業柄、
きっと、世間の感覚から、
少し、ズレているんだと思います。
普通の消費者感覚に、
軌道修正もしなきゃ・・・と、考える。
同時に、
大金持ちになっている人って、
また、違った物事の見方をするんだろうな・・・とも、考える。
今の自分の感覚は「通り道」に過ぎない。
色んな人に、生きてきた時代背景や、環境からくる「普通の感覚」が存在している。
だから、
それぞれの「常識」から、
ひとつの物事を多面的に見れるようになりたいな..
そう思っています。
子供が見たら?20代が見たら?80代が見たら?どう思うのか?
女性が見たら?
外国人が見たら??等々。
色んな消費者の気持ちがわかるようになって、
そのうえで、一番ベストな選択ができるよう、訓練を心がけています。
・・・
あとで、調べてわかったのですが、
私が「マンション」と思っていたのは、実は、東宝・ゴジラ・ビル内のホテル。
このゴジラが、正面に見える部屋や、
「ゴジラルーム」とか、あるそうです。※1泊5万円!
なるほど・・・
そうゆうことだったのかー!
2017年5月28日 22:27
前職の船井総合研究所・創業者の船井幸雄氏は、
成功の3条件として、この3つのことを挙げています。
あなたは、素直ですか?
=意見を受け入れ、やってみる、ということができますか?
あなたは、プラス発想ですか?
=過去よりも、もっと良くなる未来を見ていますか?
あなたは、勉強好きですか?
=いつでも、どんなことからも、学ぶことができますか?
この3つの質問に、
ひとつでも「NO」がつく会社・経営者からのコンサルティング依頼は、引き受けてはいけない。とも、
話しておられました。
そうゆう人に対して、いくらコンサルティングしても、
業績が伸びることはないからです。

さて、、
何年間も続く、勉強会での一コマ。
ティータイムに、熊本の農家さんから直送のメロンを出していただきました!
この勉強会で幹事をしていただいている経営者様は、
まさに「素直・プラス発想・勉強好き」が、歩いているような人。
今日のティータイム中、
自分の老眼がすすんでいることについて、勉強会の仲間と話していました。
そのなかで、ふと、こんな表現をしておられました。
「こうやって、離すと、良く見えるんだよー」
(私は、聞き逃しません!)
プラス発想が、体の奥まで染みついていて
もはや「見えない」なんて言葉が、出てこないレベルとなっている・・・笑。
すごい方です。
いつも頭が下がります。
2017年5月19日 22:46
葬儀社のスタッフさんには、
実際の年齢よりも、若く見える人と、
そうでない人がいます。
特に、私たちのご支援先には、一般的なセレモニースタッフと比べても、若く見えるスタッフさんが多い(・・・気がする)
※身内びいきも、甚だしい??・・・笑

物理的に「細胞が若返る」方法があるそうです。
そのためには「テロメア細胞」という細胞を伸ばせば良いそうです。
では、具体的に、テロメア細胞を伸ばすためには・・・
1・良質な睡眠
2・人とのつながり(孤独は良くない)
3・野菜中心の食生活
4・軽いランニング(有酸素運動)
5・瞑想と深呼吸
6・プラス発想。(悲観的な人は「テロメア」が伸びない)
うんうん。
1は、儲かる体質になって、環境整備が進めば、できること。
2は、施行件数が多ければ、OK!
3は、プライベートで、心がけてください。
4は、販促活動や、施行準備で。
5は、会社の行事やルーティーンに入れてみても面白いかも??
6は、ご支援のなかで、常にお伝えしています。
なるほど~。
テロメア細胞が、ぐーーーんと伸びる仕事をしましょう。
2017年5月7日 23:01
誰だ?
この人?

半日、京都に行きました。
観光目的でなく、突然、彼に会いたくなって・・・笑
大学3、4年生の2年間、住んだマンション近くの「餃子の王将」のオヤジさんです。
当時は、「ショーケン、萩原健一さん」の雰囲気があったけど・・・。
今でも、面影あるなー、カッコええやんー!!
ラジオから流れる音楽が、自分の知っている曲なら、
それにあわせて、必ず、鼻歌を歌う♪♪
※歌詞は、テキトウ
お客さんが来ると
「お、今日は、休み?」
「いつもの定食でええな?」
「遊びに、出かけへんのか?」
※それ以上の、しつこい会話はしない
お客さんが途切れると、
オモテに出て、軽く息抜きをする仕草も同じ。
学生時代の自分や、その延長のような、
男子・一人客が、相変わらず多く、、
20年以上、ずっとこんな風にやってきたんだろうなーと想像できる。
何年間も、
楽しそうに、料理を作り、会話をして、、。
「ひとつの仕事を続けるって、素晴らしいなー」ってことを、改めて実感。
20年後、こんな大人になっていられるだろうか?
2017年4月9日 23:18

葬祭ホールの出店が決まると、
経営者・幹部の皆さんが、必ず頭を悩ませるのが、「近隣対策」。
抑えるべきところは、きちんと抑えて、
法令、条例に基づき、粛々と対策を講じて、進めることが王道。
でも「熱心な」反対者が出ることも、しばしば。
そんな「反対派」のお宅を訪問した際の、ひとコマをご紹介。
反:「オマエら!“自分の家の隣に、作られたくない施設ランキング”が、あるのを知っているのか!」
葬:「いえ、存じ上げません・・・」
反:「あるんだよ!ネットで調べたんだ!」「葬儀場が何位か、知ってるのか!」
葬:「いえ、存じ上げません・・・」
反:「4位だよ!」
葬:「そ、そうですか・・・」
※内心(・・・あらら!!1位じゃなかったんだ~!
俺たち、意外とイケテルほうじゃんーーー。嬉しいな~。)
ストレスを感じることの多い「近隣対策」で、
葬儀業界に身を置く方が、少しだけ明るい気持ちになる、
ご支援先でのエピソードでした。
ちなみに・・・
5位、パチンコ店
3位、ラブホテル
2位、お墓
1位、風俗店、キャバクラ
2017年4月2日 8:46

春は、別れと出会いの季節・・・。
今回は、ご支援先の社長が、SNSに投稿されたコラムを、そのまま転記します。
↓↓↓
コラムを読んでくださりありがとうございます。
「お別れの時、去る時」というのは、「人の本性が一番現れる時」と言われているそうです。
これを聞くと、どのように人の目にうつるのか怖い!
という人もいますよね・・・きっと。
先日、当社の優秀な社員、●●さんが結婚退職、遠くに引っ越されるので、送別会を行ってきました。
●●さんの本性は・・・誠実な印象そのまま、でした。
彼女は、前面に出る方ではありませんが、「縁の下の力持ち」タイプ。
チームワークを大切にして、しんどいときでも、笑顔で誠実に対応されていたので、
上司・同僚・部下からとても頼りにされていました。
また退職の際にも事前に上司と相談しながら、
慎重に話をすすめられ、ぎりぎりまでお店のことを気遣っておられたようです。
信頼感、存在感の大きさというのは、
接する期間の長い、短いだけではなく、その人のあり方、姿勢によって大きく変わるものだなあ、
と改めて彼女から学ばせてもらいました。
●●さん、大阪でも●●さんらしくがんばってください!
戦友として一生、応援していますよw
もちろん、●●さんが抜けたあとのお店も、
見えないところ、見えるところで精一杯応援します!
↑↑↑
自分は、去る時、どうだっただろう??
転職は、一度きりだけれども、、
前職の先輩も、後輩も、同僚も、時々、飲みに行こう!と声をかけてくれるし、
いつでも、こちらから声をかけることもできる。
当時の社長や、取締役にも、当社でご講演いただける間柄ですし、、。
私の本性は・・・まあ平均点くらいかな?
2017年3月28日 7:31
先日のブログの続き。
ご支援先の式典には、
女子ソフトボール・日本代表元監督。宇津木妙子さんが
ゲスト講演に来られていました。
この講演会を聞きながら、
書き留めたメモを、転記しておきます。
・「負けず嫌い」が、自分を成長させてくれた。
小学生のとき、先生との個人面談を終えた親から
「アンタが、恥ずかしい」と言われ、奮起した。皆さん自身はどうか?皆さんの子供は?
・「自分の得意分野で一番になる。」と決めてから、道が拓けた。
足だけは速かったから、足を活かして、塁に出ること。
声を出すことは、誰にでもできるから、大きな声をたくさん出すこと。
・企業チームは、強いだけでは成立しない。
地域に「愛されるチーム」にならないと、生きてゆけない。
挨拶をする、子供たちに教える、清掃活動をする・・・。
・毎日、選手と挨拶をすること。
スタッフの感情が、わかるようになってくる。
・監督として赴任後、早く選手を把握するためには、個人カードを作る。
家族構成や、中学・高校の球歴、得意・不得意、性格、技術。
・監督時代、シドニーオリンピックでの逆転負け。
「レフトのエラーで敗北した」という宇津木さんの発言に対して、
選手たちが反論「あれは、みんなのエラーです!」→その瞬間が「チーム」となった瞬間。
・組織に属する者は、その「組織の目的=勝つこと」のために、
どうすれば良いか考え続け、その方向に行動すること。
仲間内の愚痴だけでは、何も生まない。意味がない。
納得できないことは、先輩にも言うし、監督にも言うべきことは、言ってきた。
組織のために、自分が果たすべきことをやっていれば、何でも言える。
「やっていない」者ほど、愚痴になる、正面から言えない。
・意見が対立するときには、
根気よく意見を言い合い、やることをひとつ決める。
2017年3月11日 21:03
最近、忙しさを理由に、
お役に立たない不真面目な内容が目に余る、このブログ・・・。
「週に2回の更新」を、スタッフちゃんに、約束したからには、
内容が薄くなったとしても、なんとか守ってゆきたい。。ので、
何とぞ、ご容赦くださいませ。
忙しい分、
たくさんの「ネタ」は、メモ書きレベルで、たまっています。
今日は、お役に立つ内容だと思います。
ご支援先といつも食事に行く「とんかつ屋さん」でのワンショット

席を片づけ中、
テーブル・ボックス席を掃除するときには。
毎回、全スタッフが、テーブルの下に「体ごと」潜り込んで、拭き掃除をしています。
ホールの場合も、飲食店の場合も、どんな業種でも「掃除」の基準は、難しい。
でも、
「テーブルの下を掃除する」というルールでなく、
「テーブルの下に潜り込む」という基準を作れば、誰でもできる。
やったか、やっていないか、誰でも、判断できる。
実際、きれいになるし、
この行動を行うことで、心が変わる。
「お客様のための店をキレイに」と、言葉で言うよりも、
この行動が、そうゆう心を作る。一事が万事に通ずるのです。
わかりやすい「基準」を作って、
指示を出しているのに、
無視して、やらないヤツがいる場合は、どうする??
ふ~~、プハッーー。
2017年3月9日 21:21

スケジュール、パンパンの状態のこんなときに、予定外の仕事が飛び込んできて、
急きょ、空港に併設されたホテル泊まって、ご依頼に応えることに。
明日は、朝イチで飛びます!
チケットカウンターは、緊張しますね!笑
後ろから、ガバッ!とVXガスやられたらどうしよう!
目の前で、一人の女性が気をひいて・・・とかされたら、
一発で、策にはまること、間違いないもんなー。。。
・・・
笑っているアナタも、きっと同じですよーー!
2017年2月15日 9:07
今月のANAの音楽プログラム。
「ウエディンベル」に「サムデイ」「卒業」「クライオン・ユアスマイル」・・・
GOOD!

今月は、ANAだけでも5回は、搭乗することになるから、
楽しみが増えました♪♪
機内では、時間に余裕のあるときには、
プログラムの「落語、全日空寄席」を聴いて、話術・古典・人情?等々の勉強をしています。
月に1度の定期訪問先が多いので、
2月は、忙しい。営業日数が28日しかないから、物理的にこなしきれなくなるのです。
機内でもパソコンやノートを開いて、仕事をしないと、間に合わない。
そんなとき「落語」は、頭に入ってこない。
なじみのある音楽が、モチベーションを上げてくれます。
新幹線移動のときには、、メールへの返信ができるから、ちょっと便利。
返信内容が、即・売上アップにつながる案件が多数なので、真剣に考えて返信する。
1本の返信に、10~15分はかかる。
1日10本に返信したとすれば、、合計で100分~150分!2~3時間の仕事。
これが、1日20本とか、なっていると、もはや、半日仕事。
じっくり考えているうちに、送信を忘れていたり、
後回しで良いものはそのままになっていたり
・・・と、大変申し訳ないことも、多数あるのです。
特に、特に、
社内のメールは、お客様優先で対応しているので、
どうしても、後回しになりがちで・・・申し訳ない。。
新幹線がトンネルの中に入って、電波が悪くなり、返信できなくなると、
その間に、携帯に入っていたライン等への、返信をはじめる。
そして、トンネルを抜けると、また、パソコンに戻る・・・。
3月末ごろまでは、そんな日々。
岡山~広島・山口は、トンネルの連続で、日本一仕事ができない路線。
。。イライラするから要注意。
で、
こんな時期に、当事務所からアベックで新婚旅行に行くヤツらがいる・・・(アベック~~!)
「連絡、つきますから!」って、言ってたから
いっぱい、ハワイに仕事の連絡したるねん(笑)!
2017年2月10日 21:22
クライアント先の「年度方針発表会」で、いただいた表彰状。。

表彰状を、
人生で初めてもらったのは、小学5年生のとき。良く覚えている。
写生コンクールで、加古川市の銀賞か銅賞か・・・を、もらった。
(牛の絵だったなあ~。今思うと、肉牛だな。)
「自分は、ダメなほうの人間だ・・・」と思っていた内気な中西少年に
「あ、、意外と、俺もやれるのかも!」という「自信」のかけらを芽生えさせてくれた。
大人になってから・・・ほとんど表彰されたことってない人生。
船井総研に勤めていたころには、
毎年、表彰の対象になるキャンペーン的なもの(何かを売れ!的な・・・)は存在していたけれども、
斜に構えて、お付き合い程度に、こなしていた「不良社員」。
「ご支援先の業績を上げるコンサル力や、生み出したノウハウの質を評価するキャンペーンがあるなら、
優勝目指して本気でやるけど、営業マンとか、販売員みたいなキャンペーンには、俺、参加しないよ~!」
な~んて。
仕事の本質を追求しすぎる??とっても嫌なヤツだったわけです。
実力がなくなると、すぐに切られるタイプですね。。
本気を出して、たまに1位をとることもあった。
それは、キャンペーンについて、
会社や上司に対して「クソっ!コイツ・・・腹立つ!」ってことがあったとき。
その理由は・・・・
表彰と同時に、壇上で何か話させてくれるから。
そのとき「全員の前で、思いっきりイヤミなこと、言ってやろう・・・」という不純な動機で(笑)
でも、そんなときに限って、インタビューなし・・・。
不純な動機、察知されていたのか、
神様が「それを言うと、ダメだよ」と、導いてくれたのか、、
今回の表彰状は、
子供のころのように「ただ、ただ、嬉しい・・」感謝です。
いつも打ち合わせさせていただいている皆さんの顔が、思う浮かびます。
わざとらしーく、誰かの目につくところに、置いとこう。。笑
2017年1月20日 21:02

社会人になって、2年間は、死ぬほど仕事をした。
会社には、寝袋があり、週のうち1~2日は、終電にも間に合わず「泊まり込み」での仕事。
色んな先輩からもらう「圧倒的大量」の仕事を、納期までに仕上げる。
「仕事を断ってはいけない」という暗黙の了解。。。
もし断ったら「アイツ、断ったらしい・・・」という事実は、先輩方全員の知るところとなり、
仕事は、一切まわってこなくなる。
さすがに土日は、昼前くらいに出社すればいい。
クライアントへの調査・提案結果をまとめた資料を提出する「報告会」前でなければ、
土日は、21時とか22時には帰社できた。警備員のオッチャンとは、めちゃめちゃ仲良しになった。
同じ部署の先輩は、優しかったので、
2週間に1回くらいは、完全に休める日がある。
そんな休みの日には、ここぞとばかり、昼まで寝て、
昼前に起き出して、この喫茶店に出かけていって、新聞や雑誌を読んで、まったりする。。。
家にいると、電話がかかってきて呼び出されるので、外に出ておいたほうが安全!
これが「隠れ家カフェ」好きの原点。。
自分のもとに、クライアントから依頼が来るようになって、
スケジュールが半分以上、つまり週に3日くらい埋まってくると、
先輩からの仕事を、選んで断れる雰囲気が出てくる。
そうなってきたのが、3~4年目。
土曜か日曜には、この喫茶店に出かけて行って、
新聞を読んだあと、自分のクライアントさんのための仕事をするようになった。
そのレトロ喫茶店、
立ち退きのため、閉店に。。。
たぶん最後になるであろうこの雰囲気を、初心を思い出しながら、懐かしむ。

2017年1月9日 21:02
「眠らない街・歌舞伎町。欲望渦巻くこの街で繰り広げられる様々な・・・」

年末年始、必ず見てしまうテレビ番組のひとつが、
「ナントカ警察・24時」もの。
ナレーションの声も大好き。
「お約束フレーズ」をつぶやきながら、
「警察24時マニア」にとっての「聖地巡礼」
年末年始のテレビ番組と言えば、
「詐欺師と直接対決する」シリーズや、
「プロ野球戦力外通告」は、必ず見てしまう。
詐欺師は、パチンコ好きが多い。簡単に土下座する。
プロ野球選手は、怪我から二軍生活が始まる。良い家に住み、良い車に乗っている。奥さんがキレイ。。とか、
自分が詐欺師に騙されないように・・・、自分が戦力外にならないように・・・と、観ています。
さて、
「古い手帳のメモ帳で、新しい手帳に書き写すほどではない言葉」シリーズ、最終回は、
テレビ番組で聞いた言葉。
林修先生(今でしょ)の言葉とある。
「なぜ、受験勉強が必要なの?」という少年からの問いに対して、こう答えている。
受験は、1ヵ月、1年、期間限定で頑張れば、良い。
社会に出ると、1年だけでなく、10年、一生、エンドレスで頑張ってゆく。
受験は、答えのある問題を解く。
社会では、答えのない問題を解決してゆく。
受験で、1ヵ月、1年、頑張る人は、社会で、10年、一生、頑張れる可能性が高い。
受験で、答えのある問題を解いた人は、答えのない社会で、結論を導き出せる可能性が高い。
つまり、受験勉強をすることは、
社会に出て、一生を豊かに過ごすための「練習」をしているということ。
合否よりも、
それを、体験したこと自体に、とても大きな価値がある。
そうゆうことなのでしょうね!

少し、打っていこう!
パチンコじゃないですよ、ボールを。
2016年12月29日 22:00
年の瀬が押し迫まるなか、2016年、最後の出張です。
帰省客の大混雑のなか、移動です。
帰省風景の車中、パソコンで仕事・・・も、なんだか野暮ったいので、
鞄に忍ばせておいた、司馬遼太郎さんの文庫本を読むことに。

写真の内容は、正岡子規の言葉。
「人間は、最も少ない報酬で最も多く働くほど、エライ人ぞな。
一の報酬で十の働きをする人は、百の報酬で百の働きをする人よりエライのぞな・・・」とある。
司馬さんは、この言葉を、子規の言動を記録した遺稿のなかでも
「もっともすぐれたものであろう」と紹介している。
江戸から明治にかけての士風について、他にも記載がある。
「武士には、捕吏がいらないというのは、本当か?」と、朝鮮通信使が尋ねたそうだ。
武士は、縄目の恥辱を受ける前に、切腹する。
「武士は、学問はそれほどなくとも、日ごろから体を鍛え、
いったん国家の大事があれば、命を捧げることを承知していた」と勝海舟が振り返る。
「禄(給料)は、将来の戦死を含む戦場での働きを見越した前渡金であって、
家臣としては、武功をたてるか、討死することで、やっと貸借対照表がゼロになる」
・・・
報酬に対する考え方、
コンサルタントとしての矜持、仕事する人の基本。。。
奇しくも、隣席に「電通の社長が辞任」という見出しが躍る新聞を読んでいる方がいる。
法律がある。
でも、その法律やルールを作った「国」自体が、借金まみれ。
彼らの言う通りにして、会社は、個人は、果たして大丈夫か?同じようになるのでは?
自分の父、祖父、曾祖父の世代に色濃く残る、
日本の士風的思考が、働き方のベースとなり、今、豊かな経済大国になれた。
まず「日本が日本である所以」を、見直して、大切に植えつけたほうが良い。
「社会問題になっているから、当社も規定通りに・・・」などと、
安易にやってしまう会社は、数年後、泣きを見る気がしてならない。
2016年12月22日 10:04

クライアント様からいただいたステキなプレゼント。
世界のビールの詰め合わせです。
事務所の雰囲気に、ぴったりの贈り物。。
ありがとうございます!
2016年12月17日 21:14

寒さ厳しい札幌で、コンサルティングの仕事。
一人で歩くときのスピード・大阪ナンバーワンと思っている私も、
雪と氷の路面では、道民の皆様と、張り合う気にすらなりません。
雪のない路面では、歩いていて、追い越されることは、
ほぼありませんが、
今回ばかりは、負けを認めます・・・。
本日、最高気温が、マイナス2度。

北海道オリジナルのお菓子を、明日の朝食のために買い込んで、次の出張地へ。
2016年12月2日 23:34
私の前職・船井総合研究所の元社長・小山政彦さんの「2017時流予測セミナー」開催前のワンショット。

当社・佐伯泰基が、小山ご本人から直々のレッスン?を受けています。
「おーい!ここに来て、小山さんに“コンサルティングの腕を上げる方法”を、質問したら?」
会場設営が終わり、一息ついていた佐伯に、声をかけて実現した光景です。
質問力は、成長力に比例します。
成長できない人は、質問しない。質問の質が悪い。
社長や幹部と、ホール回りをしていても、
それは顕著にあらわれる。
「最近、新規の会員数が減っていまして・・・ちょっと考えてみたんですが・・・」
「事前相談のポスター、変えてみました。どうでしょうか?」
「仏壇店舗の年末向けの売場、こんな感じでいいですか?」
優秀なスタッフさんからは、こんな質問がくる。
「駐車場の草が生えている、誰がいつ草ぬきするんですか?」
「バックヤードの床がめくれている、なんとかなりますか?」
「トイレが寒いと寺院に言われた」「日差しがまぶしい」「シフトのことで相談」・・・
ダメ・スタッフからの質問は、こんな感じ。
それは、自分で解決できないの?
あなた、今それ、社長・幹部に質問すること??
己の都合、保身・心地良さ・楽な業務・・・のための質問が、飛んでくる。
そして、最悪レベルのスタッフは、
コソコソ隠れるように、どこかへ立ち去っている。
質問どころの話ではない。
・・・・
さて、佐伯君、
普通のサラリーマンなら、出会えなかったような、
凄腕の経営者・幹部・コンサルタントの皆さんと、こうして知り合えることに
どれほどの価値を感じてくれているか?
かれこれ30分以上は、話していたから、
彼は、良い質問をし、
何かをつかみ、自信にもなったはず。
そして、私たち若造どもに、
分け隔てなく接してくれる小山さんに、感謝です。
2016年10月29日 21:18
先日のブログに書いた「哲学」とは!?
人生・世界、事物の根源のあり方・原理を、理性によって求めようとする学問。
経験からつくりあげた人生観。とあります。
自分よりも、ずっと賢い偉大な先人たちが、
考え抜いた原理や理論を、ほんの数時間で学ぶことができ、それを人生に活かせるのです。
物事の本質を見極め対応するために、とても役に立ちます。
その言葉は、その時々の自分に強く引っかかることがあります。
・「そうだ!自分は、間違ってなかったんだー」と、共感できる言葉
・「これは、俺に足りていない部分だな~」と、改善点を示している言葉
でも、
元々「哲学」に興味があったというわけではありません。
出会いのきっかけは、つまらない「負けず嫌い」な心です。
20代のころ、一緒に仕事をしていた先輩のこんな一言が、きっかけ。
「オレ、経営本は卒業して、そろそろ”哲学書”を読んだほうがいいって、●●さんに言われたわ~」
「●●さん」というのが、先輩も私も、とても尊敬していた取締役のコンサルタント。
先輩の言葉が、生意気なひねくれ者には、こう聞こえた。。。
(俺(先輩)は、経営のノウハウについては、卒業して良いレベルにあるから、次のステップに行けるんだ)
(キミ(中西)は、まだ、そのレベルに達していない)
チクショ・・・
俺も、テツガクショを読めるようになりたい!
そんな単純な「反骨心」が、
哲学との出会いを作ってくれました。
2016年10月6日 7:16

当社のスタッフ・佐伯泰基(さえき・やすのり)
同行したご支援先にて。
汗をかきかき、ご支援先の社長・スタッフとともに、
すぐにできる現場の改善を、あれこれ実施して、見違えるようにした後。。
彼の背中から、ハートマークの汗が!
コンサル・愛
ご支援先・愛
が、あふれだす男です。
当社の基本方針である「現場主義」を、見事に体現してくれているコンサルタントです。
2016年9月29日 22:17
骨を折って、知ったこと。<その2>
包帯を巻いた人差し指を見て、
知り合いは「どーしたの?」と声をかけてくれる。
毎回「ついに、落とし前をつけさせられました・・・」と、切り返す。笑
「悪いこと、、したんですね~」
「はい~」
一見の飲食店や、コンビニなんかでも、たまに声をかけられることがある。
驚くことに、それは、必ず繁盛店なのです・・・。
大阪の繁盛天ぷら定食屋「まきの」のホンダ君は、眉毛をカットした怖そうなザ・職人君。。
そんな彼が「スプーンで食べますか?」と大小2つのスプーンを用意してくれた。
同じく「まきの」のアオキさんは、年配のお母さん。。
スプーンで食べ始めていたら「フォークのほうがええんちゃうか?」と、フォークをくれた。
大阪の某所セブンイレブンのマエダさんは、
「指、お怪我されたんですか?」「大変ですね・・・」
レジを打った後、話しかけてくれた。
ネームプレートには「マネージャー」という肩書があった・・・。
仙台の焼肉繁盛店・仔虎で、牛丼を食べようとしたら、
店員のハギノさんが、「スプーン、どうぞ」と、にこやかに置いていってくれた。

ラーメン好きなら、ご存知の「二郎系ラーメン」の繁盛店・ラーメン荘「伝説を刻め」
お冷セルフはもちろん、はし・レンゲ・おしぼりは1か所にあり、そこに自分で取りに行くシステム、
おしぼりを捨てることまで、お客がするというローコストオペレーションぶり・・・。
そんなシステムのお店なのに、
アンちゃんが、「スプーンどうぞ!」と、持ってきてくれた。
・・・・とても、考えさせられる。。
繁盛店だから、こんな店員が育ったのか?
こんな店員だから、繁盛店になるのか?
後者である、と考えるほうが、
売上を上げることのできる経営者、幹部、スタッフだろう。
自分がすぐに「何かを変える」ことを、優先して選択する思考回路を備えている。
包帯を巻いた人がいたら、声をかける。
助けになることをしてあげる。。。
そうゆうことが、スッとできるスタッフを採用し、
そのような教育しているから、繁盛店ができるのだ。
そうゆうことができるから、より上位の役職となり、収入が増えるのだ。
上位の役職になったから、それができるのではない。
それが、できない子を入れ、
何もしない・させない店が、世の中の大多数を占める「普通~普通以下の店」となっている。
何も勉強しない、教育を受け入れる気がないと、
結果、そのスタッフも「普通以下の人生」を送ることになる。
「いや~、これは骨を折らないと、わからなかったなー」
・・・
強がっています。