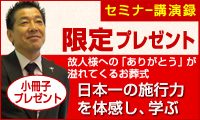2015年4月10日 8:05
春の高校野球は、
福井県の敦賀気比高校が、北陸県勢として初優勝でした。
おめでとうございます!
背番号17の松本選手が、
準決勝で、2打席連続の満塁ホームラン。
決勝で、決勝打となるホームラン。
高校野球を見ていて、
一番、グッとくる瞬間。
それは、試合終盤、代打で出てきた控え選手が、
相手の剛腕投手に、
喰らいついて、全力を出し切る姿です。
何が何でも、打ってやる!
気持ちでは、負けていない・・・という表情や、打席の動き。
そこに、普段の一生懸命な練習ぶり。
腐らないで継続してきた、心の強さ。優しさ。
一緒に練習し、そんな彼の姿を見ていた、仲間からの信頼。。。
そんなものが、全て詰まっているように思えて、
胸にグッーーとくるものがあるのです。
負ければ、次がない高校野球では、
1試合に1度は、高い確率で、このシーンがあります。
「背番号2ケタ」の選手が、いつも私のヒーローです。
で、当社も、そんなスタッフを募集中。
もちろん「補欠」で満足していちゃ駄目で、
「主力選手」になってもらわないと、ダメなんですが。
こうゆう考え方に、共感できる方を、募集!

4月中旬~、随時1次面接、
5月初旬に、2次面接・最終面接のスケジュール。
どんなヒーローに巡り合えるのか・・・楽しみです。
2015年4月7日 21:54

写真は、何年か前に行った、甲子園。
球場内のこの位置が、一番好きな場所です。
地鳴りのような歓声、ブラスバンドの応援、硬球とバットがぶつかる金属音。。。
球場内で、何が起こっているのだろう!!!
ドキドキ・ワクワク感が、最高潮になる場所なのです。
先日のブログの続き・・・「解説者で楽しむ」のは、高校野球も同じ。
特に、夏の甲子園では、名門校の監督が、ゲスト解説者に呼ばれます。
監督さんの個性が出ていて、とても楽しいのです。
人情派、熱血漢がいれば、理論派もいる。
守備重視もいれば、攻撃重視もいる。
「解説すること」が、本職ではないので、
かなりズケズケ言っちゃう監督さんもいて、楽しさ倍増なのです!
特に、年配の監督さんは、面白い。
経営の参考になるかもしれない、面白かった解説をひとつ、ご紹介します。
解説者は、広島・如水館高校の監督・迫田穆成(さこた よしあき)さん。
元・広島商業の監督として有名です。
手堅いバント戦術の生みの親。
怪物・江川の作新学院に、わずか2安打で勝利したことは、野球ファンの間では伝説です。
アナウンサーが質問します。
「迫田さんは、部員数の多い大所帯の野球部を、どうやって把握しておられるのですか?」
「全員まで、目が行き届かないのではないですか?」
迫田さん、答える。
「それはですねえ・・・、スパイを作っておくんですよ~、グヒヒヒヒ・・・」
ア)「スパイ?というと・・・?どうゆうことですか?」
迫)「監督がですねぇ、選手に、直接聞いたところで、そんなもん、選手はホンネを言いませんよ。」
「マネージャーあたりを、スパイにしとくんです」
「そこから、色んな情報を、こちらの耳に入れておきます」
「これで、だいたいのことは、把握できます」
ア)「もし、不満を持っている選手がいたら、どうするんですか」
迫)「それは、チャンスですね~」
「呼び出して“オマエ、最近思うとることがあるんやないか?”と聞いてやるんですよ」
「オマエの意見を聞かせて欲しい、こうゆうてあげたら、
次の日からチームのために、一生懸命やりはじめますよ」
いやー、さすがです!
・・・・
これは、会社でも全く同じ。
スタッフ20名以上の規模になれば、必須のマネジメント法ではないでしょうか。
そう言えば、、、
前職・船井総研時代の役員で
「普段、会社にいないのに、どうして、そんな小さなことまで、知ってるの???」という方がいました。
500名規模の組織のあらゆる部署で「何が起こっているのか」「誰がどう思っているのか」を、
ほぼ完ぺきに、把握していました。
あれも・・・・
間違いなく、営業事務スタッフを「スパイ」にしていましたね。(笑)
2015年3月7日 9:32
コンビニ業界再編のニュースが、
新聞記事に出ていました。
3位のファミリーマートと、
4位のサークルKサンクスが、統合へ向けて話し合いをスタート。

商品仕入れ、システムを共有し、
スケールメリット追及する・・・との主旨です。
「1業種で、地域の中に生き残れるのは上位3社まで。」
「そんな時代が本格化する」とお伝えしている内容が、現実味を帯びてきました。
葬祭業界の主流も、このような構造になってゆくことでしょう。
買収・合併が相次ぎ、屋号はそのままでも、
「実は、運営会社は同じ」という構造です。
この新聞記事から、数字を拾って、アレンジしてみました。
「総売上÷店舗数」で、「1店舗あたり平均年商」を計算し、
さらに、その平均年商を、営業日数365日で割って「平均日販」を算出してみました。
1店舗・平均年商 日販 ※別のデータより
・セブンイレブン・・・・・・・・2億1885万円 59万円 (66万円)
・ローソン・・・・・・・・・・・・・・1億4484万円 39万円 (54万円)
・ファミリーマート・・・・・・・1億5277万円 41万円 (52万円)
・サークルK・サンクス・・・1億3200万円 36万円 (43万円)
()カッコ内は、私が別で探したデータから、日販を計算してみたもの。
数字は、絶対に、鵜呑みにしない!
・・・という、この性格のブラックさ!!
さらには、
セブンイレブンの公表売上に対して、
「どこまでの売上をいれてるの??セブン銀行の手数料とか入れてるんじゃないのー」
という意地悪な視点もあったりして・・・。
私が計算したデータが、少し古いせいなのか、数字には開きがあります。
が、現在のところ、
セブンイレブンの圧勝には、変わりがありません。
しかも、増税後、セブンイレブンだけが、売上を伸ばしていて、
他のチェーンは、売上を落としているそうです。
何故なのか?
その理由は、どこにあるのでしょうか?
2015年2月14日 23:44
チョコが欲しいから、、、と、
コンサルティングの日程を、
わざわざ土曜日のバレンタインデーに、決めたわけじゃ~ありませんよ。

クライアント先の社長のお母様から、
チョコレートをいただきました!
「敬愛する・・・」
自分の人生のなかで、初めてもらった言葉では、ないでしょうか。
チョコよりも、この「美しい日本語」をいただいたことが、一番の宝物です。
この言葉に、ふさわしい人間にならねば・・と、
決意を新たにしています。
ご子息と共に、成長してゆきます!!
2015年1月28日 22:19
新幹線の席に座ろうとすると、、、
ボクの指定席に、1冊の本が、ポン!と置いてある。
「あれ、席を間違えたかな??」と思い、
切符を見直したけど、やっぱり、間違いじゃない。
隣の席の人が、本を置きっぱなしで、
トイレにでも、行ったのかな??
30分経っても、1時間経っても、戻ってこない。
(きっと、忘れて、降りちゃったんだな・・・)
ちなみに、その本。。。
これまで、1回も買ったことも、
読んだこともない「大富豪の習慣・・・お金持ち・・・」的なタイトルの本。
手に取って、
パラパラ~と、読んでみました。
ズキーン!!とくる内容が、、、
大富豪は、「忙しくしていない」「時間に余裕がある」と・・・・(笑)
つまり、
じ~っと、していて成果が上がるシクミを作っている・・・。
そんなことが、書いてありました。
そうかーー!
うん、そうだ。
それ!!
すぐに、方向転換すること、決定!
それ以外も、
何か色々、書いてましたが、頭に残っているのは、それだけ。
忙しい、忙しい・・・と、言い訳している今の自分に、
きっと、神様がプレゼントしてくれた瞬間でした!!
2015年1月11日 22:49
人を形づくるには「ルーツ」があります。
吉田松陰の場合、
松下村塾の創設者でもある「玉木文乃進」という、
スパルタ頑固オヤジを、外して、語ることはできません。
吉田松陰は、叔父にあたる「玉木文之進」の、厳しい教育を受けて育ちます。
有名なエピソードをご紹介。
文之進が、畑仕事をしながら、松陰に勉強を教えている。
あぜ道で、幼い松陰が、本を読む。
松陰の顏に、ハエが止まったので、松陰はそれを、手で追い払う。
すると、文之進、ブチ切れて、ボコボコに殴る。
勉強しているのは「公」のため、ハエを払うのは「私」の心。
武士の本分は、国の為に働くことにある。
武士とは、自分のために生きるのではなく、国の為に生きる。
学問を学ぶということは、公の為に尽くす自分を作るためであり、
ハエを払うということすら「私」であるというのです。
かゆみは、私。掻くことは、「私」の満足。
それを許せば、大人になって、私利私欲に動く人間になる・・・というのです。
何ら生産活動をせず、農民、町人のおかげで、生きている武士は、
命を懸けて、住みやすい国づくりを行うものだ・・・という考え方を、持っていたそうです。
「コンサルタント」の本分に対して、
私は、「玉木のオジキ」と、ほとんど同じ考えを持っています。
コンサルタントの本分は、クライアントのために、生きるにある。
365日・24時間、自分のすべての時間を、
クライアントの売上アップのために注ぎこむべきだ。
ずっと、仕事をしていなければならない。
そうゆうことができなければ、
四六時中、経営のことを考えて生活している「経営者」に対して
良きアドバイスを、できるはずがないのです。
では、世の中でコンサルタント以外の仕事に就く人たちは??
基本的には、同じだと思っています。
少なくとも、
お給料をもらっている時間は、すべて「公」のために、尽くそう。
勤務時間における「公」とは、何か?
「公」は、会社であり、
会社の先にある「お客様」と置き換えても、良いでしょう。
もし「玉木のオジキ」がいれば、
勤務中、顔に止まったハエを追い払っただけで、ボコボコだ。
喉か乾いて水を飲んでも、
おケツが痒いとポリポリかいても、きっとアウトだろう(笑)
まさか、今の時代、こんなことで怒り狂う社長はいない。
でも、携帯をいじる、私用を行う、私語で手が止まる、
「このくらいでいいか」と妥協したサービスを提供する、自分が面倒なことはやらない・・・。
こうゆうことは「私」であり、
「公」の時間からは、一切、排除しなければならない。
会社のため、お客様のためになることを、
100%以上の力で取り組むようにしましょう。
玉木のオジキ、本当にスゴイ。。。
松陰の後は、日露戦争203高地で有名な「乃木希典」を教育している。
オジキ本人は、松陰の教え子でもある「前原一誠」が、
維新後に起こした「萩の乱」に、
養子を含む教え子たちが参加したことに責任を感じ、先祖の墓の前で自害。
介錯は、大河ドラマの主人公・文の姉さん(寿)=松陰の妹にさせたと言います。

写真は、乃木希典の実家です。
吉田松陰の周りの、あんなこんなのエピソードが、
空気として伝わってきます。
2015年1月7日 8:06
先日のブログ写真に、
吉田松陰関連の書籍を、2つを載せました。
山岡荘八さんの「吉田松陰」
司馬遼太郎さんの「世に棲む日々」
人物にしても、
事柄にしても、
ノウハウにしても、それを知るためには、
1つの書籍や情報源だけでなく、
同じテーマで、複数の書籍や情報源を、見るようにしています。
たとえば、
コンサルティングで「人事制度の改革」が、必要になれば、
1つの書籍だけで満足するのではなく、
短い期間のうちに、類似書を4~5冊くらい買い込んで、読みます。
そうすることで、
自分のフィルターを通して、「本質」に近づくことができる気がします。
「オモテ」だけじゃなく、「ウラ」から「ヨコ」から、見るのです。
「営業マン」というテーマでも同じ、
「ホームページ」というテーマでも同じ。
同様に、
一人の作家や、経営者に、興味を持てば、
その人の関連本を、もうひとつ、ふたつと、読む。
「あの店が成功しているらしい」と聞けば、
鵜呑みにせず、別のルート、別の人間からも、情報を得る。
「あんこの和菓子」が美味しいと思えば、
しばらく「あんこ系統」のお菓子ばかりを、探し求め、食べる・・・
そのうち、小豆の銘柄なんかにまで、詳しくなる。
(これは、ちょっと違うかな??)
「深く掘れ、そうすれば、拡がる」
砂場の穴を深く掘り進めば、自然と穴の直径は広がってゆくのです。
ひとつの道を究めれば、
他の分野にも通ずる、「本質」とか「原理原則」に、早く行きつきます。
2014年12月14日 23:49
「どの政党が、何票くらい集めるかな?」
「負けそうな政党や候補者から、“勝たせてくれ”と、参謀約を依頼されたら、
どんな作戦を立てるだろうか・・・」
毎回、そんなことを考えながら、選挙を楽しんでいます。
選挙は「支持を集める」という面で、
「マーケティング」に、そっくりなのです。
「風」に乗るか、
「原則通り」にやるか、、、最低限、どちらかに合致しないと、
当選することは、できません。
「風」とは、マーケティングで言えば「時流」です。
「時流」にあう、商品、施設、サービスを、提供すれば、売上は上がります。
「原則」とは、「地域一番化商法」。
政治のステージで、「風」に逆らっても「勝てる」候補者は、
選挙の原則通り、地元で「どぶ板戦術」を実行している人です。
「どぶ板」とは、ひと昔前、家の前の側溝の上に敷かれていた板のこと。
この「どぶ板」をまたいで、一軒ごと戸別訪問をしていたことに由来して、
地道に、汗と足で稼ぐ票集めを、「どぶ板選挙」と呼びます。
選挙における「どぶ板戦術」の具体例は、こんなもの。
・とにかく握手の回数を、増やす。「握手の数しか、票は出ない」
・「演説会」を、増やす。(あえて、ビールケースに立ち、コートも着ずに)
・リアクションの演出(抱擁、涙、お辞儀・・・恥ずかしくなるような、行動も相手には効く)
・普段から、土日は地元に帰り、とにかく「歩く」「有権者と会う」
・普段から、買い物は、すべて地元で行う。
・普段から、葬儀(通夜)に、参列する(呼ばれなくても行けるから)。
その他、選挙から学ぶこと。。。葬祭業経営と酷似している。
・「支持基盤=会員組織」があると、やはり安定する。
・負ける候補者は、「内部崩壊=分裂・お家騒動」のあった人。
結局、外部要因(風やライバル候補)に負けるのではなく、内部要因が原因で負ける。
・地元に、自ら以上に、自らのことを考えて動いてくれる
「営業力のある」幹部がいなければ、勝てない。
葬儀社としての
「どぶ板戦術」を、見直してみませんか?
ところで、、、
選挙日の開票時間を過ぎると、
各テレビ局の選挙番組を、一気に見てゆきます。
最近、面白いのは、テレビ東京の池上彰さんの選挙速報番組。
聞いちゃいけなさそうな話に、切り込みますし、
遠慮なしのブラックなインタビューも、面白い!!
そして「毒入り」当選者テロップも、ニヤっとしてしまいます。
まだ見ていない方は、ここからどうぞ!
http://togetter.com/li/757634

今、使っているこの美味しいバター・・・
安倍首相の出身派閥・町村派のドン・町村信孝さんの
親族の会社が作っていることも、
テレビ東京の当選テロップで知りました!
2014年11月18日 9:56

「葬祭ホールに、ぴったりだろうな~」
そう思える「隠れ家・喫茶店」です。
建物は、全て本物の木材で建てられ、
植樹をたっぷりと。
そして、ライティング効果も、完璧に。
イチ消費者としては、居心地の良い空間になっています。
一方で、コンサルタントとしては、
「お金かかっているだろうなー」と想像してしまいます。
投資金額は・・・少なくとも、1億円規模でしょう。
葬祭ホール、家族葬ホールも、きっとこんな風に、
より本物に、より大きく、より便利に、なってゆくことでしょう。
「ハリボテ」ホール(=自宅の代わりにホールでお葬式ができるという機能だけ)では、
通用しない時代が、やってくるのかもしれません。
ただし
「本物素材のホール」は、とてもお金がかかる。
お金持ちしか、土俵に載れない。
コストをおさえ、
尚且つ、居心地良い家族葬ホールを作る。。。そんなことが必要だろうな。
・・・
おおっと、、
くつろぐために、「隠れ家」に来たのに、
つい、仕事の思考回路になってしまう。。。
クライアント葬儀社さんに儲けていただくための
「これだっ!」というネタを仕入れることができた瞬間が、
一番のリラックス法なのかもしれませんね。
2014年11月5日 7:48

高校時代まで、バスケット部に入っていました。
「日本は、学歴社会だ!」と、批判する人もいる。
それは、違う。と感じています。
「日本は、実力社会」なのだ。
学歴や部活動をしてきた人が、就職活動のときに評価されるのは、
勉強なら「合格」
部活動なら「勝つこと」という「目的・目標」に向かって、
努力する過程を、彼らは、知っているからなのです。
自分のやりたいことを我慢して、
どうすれば、それが達成されるか?を、
様々な工夫で、乗り切ってきたことを、会社は評価する。
だから、実力社会です。
会社とは、顧客の支持を集め、
利益を出すという「目的・目標達成集団」です。
「ただ、楽しければいい」という、
サークル活動、仲良しクラブではありません。
そういった意味合いで、
何かの成果を出すために、一生懸命やってきたという過程は、
会社の求める人材像に、近いのです。
その習慣がある人には、
「成果を上げることへの常識」が体質としてしみついているので、
イチから「当たり前」を教える必要がないから、教育がスムーズなのです。
しかし、
そういった優秀な人材は、
大企業が、持っていってしまいます。
現実的には、中小の葬儀社には、
上記のような「目標達成のための努力の過程」を経験していないスタッフが、多く入ってきます。
「習慣・体質・価値観」を、
きちんと植え付けるために「スタッフが勉強する時間」を、
小さな会社ほど、いっぱいしなければならないのです。
2014年10月16日 22:04
先日の結婚式。
最新式の結婚式場でした。
葬祭会館のレイアウトや空間設計づくりにも、
とても参考になりました!
少子化にも関わらず、億円単位の投資をして、
新規参入で結婚式場を作るだけあって、アイデアが散りばめられています。
レイアウトは、まったく顔を合わせず、
1日4組くらいは、軽く回転できそう。
一部をご紹介。たとえば、
披露宴会場に、オープン・キッチンが配置されています。

葬儀社のウィークポイント・・・お食事。
どうするか?
結婚式場は、ここまできている。
「生産の現場と、販売の現場を、できるだけ近くする」
これは、あらゆる業種業態に通じる「売上アップの真理」です。
教会の祭壇は、ほとんど花だけですしね。
その分、動きにあわせた作り込みがすごい。
祭壇タイプの立派さ・豪華さで、
受注金額を増やすのは、だんだん無理が出てくるはずです。
2014年10月11日 12:02
船井総研時代の友人の結婚式に!

とても楽しめる、素敵な挙式でした。
「挨拶」や「余興、歌」もなく、
ゆっくりとお祝いすることができました。
何を隠そう・・・
お二人の「キューピット役」は、このワタシ。
実は、今回で「キューピット」として、3組目のご結婚。
なかなかの数字でしょ?
ちょっとしたコツみたいなのが、あるんです。
キューピットとは、「2つの存在を結びつける媒介者」
「媒介」は、コンサルタントとして、重要な言葉なのです。
コンサルタントは、「良い方向に導く媒介」であれ。
そう思っています。
「お客様」と「葬儀社」の媒介役となり、
お客様が魅力を感じ、
葬儀社の良いところが出る「サービス・商品」「販促物・販促法」を造形する。
「トップ」と「社員」の媒介役として、
双方の意向が反映された「もっと良い別のモノ」を生み出す。
「今」と「将来」の媒介役となり、
思い描いた未来像への道筋が、明確に見えるように提示する。
「求職者」と「使用者」の媒介になることもあれば、
「父」と「息子」、「夫」と「妻」の媒介になることもある。
最高のコンサルティングとは、
「当事者をして、進行せしむる」こと。
←ちなみに、これ・・・師匠の言葉です。
コンサルタントが、媒介となり、
当事者同士で、前に進むような空気を作ること。
コンサルタントなしで、
自分たちで売上が上がるようになるように。
これは、葬儀という場でも、同じではないでしょうか?
葬儀社が前に出ることなく、
施主様が故人様と、
良いお別れができるような空気を作る「媒介」となる。
「良き媒介」
それを、心がけています。
2014年8月7日 7:20

最低賃金が、また上がることが確定。
そんな新聞記事が出ていました。
しかも、
これから毎年・毎年10円以上、上げてゆく前提だそうです。
ただでさえ、
円安で輸出を主体とする大手企業が潤い、
求人を増やしているため、
葬祭業界には、非常に、人が集まりにくくなっています。
追い打ちをかけるように、政府の「最低賃金の引き上げ」政策。
つまり、募集広告に表示する「時給」「月給」は高くせざるを得なくなり、
それに伴い既存スタッフの人件費、
さらに保険等の諸経費も上げざるを得ない。。。という状況が起こってきます。
個人的意見として、
この「最低賃金」には、多くの問題点があるんじゃないかなーと考えています。
たとえば、「県単位」ということが、現実に即していない。
ご支援先エリアでの一例を挙げれば・・・現在、千葉県の最低時給は777円。
(ちなみに、24年の時点から21円も上昇しています。)
しかし・・・
千葉市や浦安市、船橋市等ならまだしも、
房総半島の端っこの、鴨川市や銚子市、東金市・・・といった田舎型の町までも、
すべて一律777円となっているのです。
以前から、あまりにも、乱暴な決定方法ではないか・・・と思っています。
しかしながら、
もはや、この枠組みの中で、スタッフを集めてゆかなければなりません。
結論的には、
時給を上げても、利益が残る体質を作り上げることが、
方法論としての王道だと思います。
2014年8月1日 20:07
その時代が「好景気なのか」「不景気なのか」・・・
景気に対応して、マーケティング手法も、
若干変更を行うことが必要です。
たとえば、今は「好景気」と言われています。
好景気のマーケティング原則のひとつに
「不景気のときには、売れなかった高価格帯の商品が、売れ始める」
知ってか、知らずか、
各メーカーが、「最高級品」を投入し、
行列ができるほど、売れています。
ポッキーも、ポテトチップスも。
私は、「世界一、美味しい」という、ふれこみの
最高級コーラ「キュリオスコーラ CURIOSITY・COLA」を、飲んでみました。

1905年、イギリスで創業した老舗の飲料メーカーの商品。
人工甘味料を使わない、ノスタルジックなコーラの味がします。
味オンチのため、チェリーコーラと飲み比べてみましたが、
その差は、歴然でした。
景気に対応して、
マーケティング手法は、変えてゆくものです。
上記の原則の他にも、様々な景気対応の原則があります。
一部をご紹介します。
「ビジネスユースや、マニアユースだった商品が、一般に普及をはじめる」
「不景気時代、ディスカウント系で鳴らした会社が、専門店へと進化する」
「募集をかけても、スタッフが集まらない。人材育成に注力する」
ひとまずは、
「好景気」と言われている今、「最高級のお葬式」を、
「世界一、恩返しのできるお葬式」として、投入してみませんか??
2014年7月19日 21:30

なんとも強気なポスター・・・。
我々、葬儀業界も、
このくらい強烈なメッセージを発したいところ!
「親の葬式だろ?
親族にも、ご近所にも、葬儀に来てもらえ!この野郎!」
今回も、酔いどれ・経営談義・・・
テーマを「売上」から、「利益」に移し、
経営を、一刀両断にしてみたい。
「利益」とは、スタッフの成長の証拠です。
一人のスタッフが、
以前よりも、無駄なく・効率よく仕事ができるようになれば、
会社に利益が残ります。
少しでも、良いアイテムを販売できるようになれば、
同じ手間と原価で、利益が残るようになります。
売上を上げるために、ホールを作れば、お金がかかる。
営業マンを増員しても、お金がかかる。
チラシ・DMを出せば、お金がかかる。
でも、「販売のフレーズ」を、
今いるスタッフさんが、お客様に伝えることができれば。
コスト・ゼロで、売上がアップし、
それは、そのまま「利益が増えること」になるのです。
このような、
0円でできる「言葉の力」は、スタッフの成長の証と言えます。
経営幹部は、どんな新人スタッフでも、
簡単に発することのできる言葉を、
設定してあげて、現場に明快な指示をだすこと。
現場スタッフは、その指示通りのフレーズを、
きちんと100%全員のお客様に、声かけすること。
まさしく「会社としての底力=人財のパワー」。
これによって、
会社に残る現金の額が、大きく変わってきます。
2014年7月10日 19:02
野球つながりで、
記憶にとどめておきたい話を、ひとつ。
巨人軍監督・原辰徳さんの父・原貢(みつぐ)氏が、
先日、逝去されました。
「三池工業」
夏の甲子園・歴代優勝校のなかに、耳慣れない高校の名前あります。
昭和40年のことです。
実は、この高校こそ、原貢氏(当時31歳)が、監督として率いた高校です。
炭鉱の町の公立の無名校を、全国優勝にまで導いたのです。
その後、実績を買われ、
無名であった東海大相模高校の監督として、迎え入れられ、
甲子園出場に導き、再び全国優勝を成し遂げる。

その後、息子・原辰徳が、同校に入学すると、
非常に厳しく、鍛えたことは、有名です。
辰徳への1000本ノックは、特に熾烈を極めたといわれ、
他の野球部員を引き締めるための、見せしめとして、
中心選手であった息子を拳骨で殴る、倒れれば、蹴るということもあったそうだ。
教え子たちへの言葉も、多い。
「今、スタメンであることは、重要じゃない。花が咲く時期は、選手によってマチマチだ。」
「チャンスに、打てる打者こそ、良い選手。」
「野球も人生も、絶対に逃げちゃ駄目だ。」
「結果の為には、過程が大事。だから、日頃から一生懸命、練習しなさい」
「お前もつらかっただろうが、俺もきつかった」
これが、原辰徳の高校生活・最後の試合に負けたときに、かけた言葉。
原辰徳は、現役を退いたのち、監督となり、
巨人を強くし、日本代表監督としても、世界一に。
監督としてのDNAも環境も、素晴らしいものがあるのだろう。
さて、経営の話。
原貢ほどのレベルで、後継者に接している経営者は、
どのくらい存在しているのだろうか?
息子を、社員以上に、甘やかしていることはないだろうか?
また、原辰徳のように、
父親のシゴキに耐えられる後継者は、存在しているのだろうか?
実家だからと、
普通の会社に勤めている以上に、甘えていることはないだろうか?
父も子も、能力のあることを「親子鷹」という。
そのような親子経営者を知っているが、
そうでない同族経営の会社も、実際のところ多いものです。
育てる側の覚悟、育てられる側の覚悟。
夏の高校野球が始まる季節、ふとこのようなことを考えるのです。
2014年6月22日 9:24
台風が来て、街路樹が倒れた。
なぜ、街路樹は、倒れてしまったのか?
「強い風が吹いたから」・・・これは、「契機=きっかけ」。
「根が腐っていたから」・・・これが「真因=本当の理由」。
契機と真因は、
よくちゃまぜになって、会話されています。
仕事の会話をするときに、
ここを混同すれば、噛みあいません。
たとえば「お客様アンケート」の
「なぜ、当社を選んでいただいたのですか?」という設問への、
回答にも、「契機」と「真因」が、入り乱れています。
「チラシが入っていたから」
「事前相談をしていたから」
「価格が明瞭と聞いていたから」
「以前、参列したことがあったから」
「会員だったから」等々・・・。
契機と真因を、明確に整理して、お客様の声を聞くことが、
その会社に応じた、優れた戦略・戦術を作るための原動力となります
自分を取り巻く出来事に関して
いつも、曖昧にしないことが大切なのです。
「契機」も「真因」も、両方が大切。
でも、何度も同じ失敗が起こり、
成長できない会社や人には、
どちらかと言えば、「真因」を探ろうとする習慣がありません。
その現象の理由を「きっかけ=契機」だけで、
見ていることが多いように感じます。
根っこに横たわっている真の理由は、なんだったのか?
それは「契機」なのか「真因」なのか?
「どうしてそうなったのか?」を、少なくとも三度は、
自分と他人に問いかけ、真因を追究してみましょう。
2014年6月8日 19:52
先日の記事の続きです。。。
40年間、成長を続けているある経営者の具体例をご紹介します。
たとえば、仕入れ材料の梱包。
自社で廃棄すれば、有料となるので、予め解いて納品してもらう。
この「一見、ケチに見える」経営者が、
機械の故障で何日も生産ストップすることに備えて、
予備の機械を購入している(ただし、中古品ではあるが・・・)
いつでも、誰でも仕入れることができる商品は、
その都度、安く仕入れる。
しかし、わかりやすいネームバリューのある商品は、
高くても買う。
それも、すべて買い占める。
「うちしか扱っていません」と、他社が扱えないようにして販売できるから。
昔、お世話になった船井総研では、
故・船井幸雄会長が、こう話していました。
「経営者という生き物は、みんなケチである」
「また、そうでなければ、優秀な経営者と言えない」
「だから、コンサルタントは、サラリーマン感覚で、経営者にアドバイスするな」
会長の言いつけを、素直に守って、
サラリーマン時代から、真面目に「経営者感覚」で仕事してきました。
「普段、ケチだけど、将来の売上のために、行くときは、行く」
これが長続きする=何年にもわたり、周囲に、お金をたくさん払える経営者。
「普段、気前が良くて、行くときに、行かない」
これが、最終的に従業員を路頭に迷わせる経営者。
そんなふうに、なっています。
2014年6月7日 22:39
経営コンサルタントをはじめて、
20年が経とうとしています。
業界内外の色んな会社、色んな経営者、色んなコンサルタントを、
かなり真剣に間近で、見てきたという点では、そこそこの自信があります。
たった20年のうちだけでも、
地域・業界では「栄枯盛衰」が、繰り広げられています。
今は、調子がいいけれども、必ず駄目になってゆく会社・人。
今は、イマイチだけど、これから伸びてゆく会社・人。
安定成長を、続ける会社・人。
浮き沈みが、激しい会社・人。
できるだけ、事実に基づき、
客観的に(と、言っても、それが主観なのですが・・・笑)、
特に、中小企業において、
時代が変わっても、
安定的に成長しているそれらの特長を、ルールとして、とらえています。
そのうちのひとつが、
「ローコスト・ハイコストの使い分けに、基準がありメリハリが効いている」というもの。
お客様の目に見える部分は、ハイコスト。
お客様の目に見えない部分は、ローコスト。
たとえば、店舗には、お金をかけるが、
バックヤードには、お金をかけない。
売上につながる部分は、ハイコスト。
売上につながらない部分は、ローコスト。。。
こんな哲学を持っています。
2014年5月25日 22:00
京都市内で、
出店候補地を物色中に・・・。
歴史ある、ワタシ好みの建物を発見しました!
看板を、よーく見れば・・・
おぉ、「任天堂」と書いてあります。

ファミコンやゲームボーイ、DS、Wiiなどなど、
テレビゲーム関連の商品が主力の「任天堂」の本社のようです。
看板にある通り「任天堂」は、
元々は、花札・かるた・トランプ等を作る会社でした。
創業から100年以上の歴史がある会社です。
「社是・社訓は、作らない。時代に対応するために」
「経済界への政治的活動は、行わない」
「多角化失敗の歴史から、異業種進出は、行わない」
こんな方針があることでも、有名です。
新しいものを生み出し「変わってゆくこと」こそが、
企業の生き残りの条件であることを、改めて実感しました。
「進化論」のダーウィンが、
残したと言われている名言を、思い出します。
強い者が生き残るのではない、
賢い者が生き残るのでもない、
唯一、生き残ることができる者、それは変化できる者である。