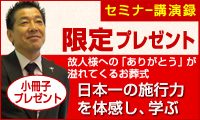2014年10月7日 21:27
クライアント先の社長に、
コンサルティングの次の日、
善光寺の「お朝事(おあさじ)」に、連れて行っていただきました。
早朝5時に、
宿泊しているホテルの前まで迎えに来てくださり、
共に参拝してくれました。
本当に、ありがとうございます。
当社の玉川と3人で、
爽やかな朝の空気を、全身に吸い込んで・・・。

名物の「お数珠頂戴(おじゅずちょうだい)」にも参加。
朝、本堂に入るご住職に、
数珠で頭を撫でてもらうのです。
これで「グレートパワー」を、授かることができるというもの。

ちなみに、
おみくじは、玉川と2人そろって「大吉」!
さっそく、お数珠のご利益か。
社長に教えていただいた「長野県人の誇り」。
国宝である善光寺の本堂。
そんな価値ある建物に、
24時間、本堂に近づける。触れる。
この本堂には「誰も、見ることができない」
とても貴重なご本尊の「絶対秘仏」がある。
このご本尊を入手したいがために、
過去、いろんな権力者たちが、これを持ち去るため、
「秘仏」は、各地を転々として、。
それなのに、
塀も柵も、一切なし。
24時間、施錠されることがない。
このような「国宝」の管理方法、日本のなかでも、珍しいのでは?
さすがは、日本一の教育県・長野県です。
会社も、こんな良心に基づいた経営をしてゆきたいものです。
2014年10月2日 7:46
「隠れ家カフェ」を、発見!
カウンターで、ゆっくりくつろげます。

「酔った勢い」で・・・
いや、あまり飲めないから「酔ったふり」で、
ドロドロしたホンネを、書いてみたい。
モノマネが「成長の最短距離」と、最近のブログに書きましたが、
自分のノウハウが、パクられて、ニセモノが出回っている。
つまり「モデル」とされている。
ただ、私の知らないところで。。。
クライアント先葬儀社さんや、会員メンバーさんには、
提供するノウハウを、たくさん使ってほしい!!
しかし、
知らない印刷会社が、
当社が提案して、ご支援先・葬儀社で制作したチラシ・広告、WEBのデザインを、
横流しして、他の葬儀社から、受注している。
業界向けのセミナー講師が、しゃべっている中身は、
私のノウハウを、そのままコピーしたようなもの。
私が作ったテキスト・資料を、
驚くことに、そのまんま自分のセミナーのテキストに
掲載している某コンサル会社のコンサルタントまで、存在する。。。
昔から、私のノウハウは、良くパクられる。
船井総研に所属していた頃、
先輩が、勝手にマネして平気でいる
・・・なんてことは、ザラにあった。
良くパクられるの、シンプルな理由だ。
質の高いノウハウだから、パクられる。
誰でも、どこでも、すぐに効果が出るよう、
使いやすく高められているノウハウだから、パクられる。
こんな自負もあるから「負けるもんか!」と、
さらに、新ノウハウを作る。。。けど、腹が立つ。
あるエッセイで読んだことがある。
「ホンモノの質と、ニセモノの質は、比例する」
ニセモノも評価され、食べていくことができている・・・という事実は、
それだけ、ホンモノ(=自分)の質が高いということ。
と、ドロドロした心をクリーンにしようとする。けど、腹が立つ。
まだまだ、人間ができていない証拠だな~。
先日のブログにも書いているように、
自分も、パクることを「是」としています。それが成長のコツです。
でも、自分なりの「ルール」を持って、パクるのです。
特に、自分が直接の利益を得ることができるような内容や、
同業界のノウハウならば。
それを紹介して、
この「中西の内面のブラックな部分」を、
吐き出したブログを、終わりたいと思います。
「地位・名誉」「お金」「仁義」
この3つのルールを、守っています。
「地位・名誉」
自分がマネしたり、参考にした内容を、他に紹介する際には、
「実は、○○さんに教えてもらったことなんです。
素晴らしい方です、是非、注目してください」
「この本、いい本ですから、読んでください」
「●●さん、直伝のノウハウです」とか。。。
ネタ元の株が、上がるように、配慮しているのです。
それが、ネタ元の耳に入って、
とても信頼度が上がる・・・ということが、たまにある。
「お金」
マネさせてもらったネタ元には、
「経済的メリット」が行くよう配慮する。
講師に招いて講演料を渡したり、セミナーに参加して会費を払ったり、
特別扱いで情報・資料提供&コンサルティングしたり、
オイシイ得意先を紹介したり・・・。
なんだかんだと、ネタ元にお金が回るように、取り計らう。
「仁義」
「これ=Aを、使わせてもらっていいですか」の一言をかけてから、真似する。
それは、当然のこと。
さらに、Aをそのまま使わない。
自分なりの考えや、別のもの=Bを、組み合わせることで、
もっと良いもの=Cを作り出して、使うのです。
で、パクらせてもらった元に、Cをお返し・報告する。
「Aを元に、こんなCを、作ってみました。よろしければ、是非・・・」と。
真似しているだけの人は、経済面で成功しても、
尊敬されることはない。
どこか、少し、蔑んで見られている。
「真似する」にも、矜持というものがある!
「あーあ、小さい男だな・・・」と、我ながら思う(涙)
でも、そうゆうところを大事にしないと、良いモノを生み出す仕事はできない。
面倒臭いことだけど、そう生きてゆきたい。。
と、自分を納得させています。
・・・
ブラックな内面に、お付き合いさせてしまい、
申し訳けありませんでしたー!
2014年9月23日 9:19
ワイシャツの袖を
「腕まくり」して、仕事するのが、なぜか大好き。
夏でも、冬でも、なぜか、腕まくり。
本当のマナーからすれば、
やっちゃ駄目な服装スタイルですが、
やめられない・・・。
入社2年目くらいまでは、先輩から
「正人ー、“一生懸命、やってます!もう仕事をふらないでください”を
必要以上に、アピールしてるんやろー(笑)」
「無駄やで、はい、仕事あげる!
さあ、今週は何日、家に帰れるかなー」
「可愛がり」を受けていました(笑)
裏地にデザインのある「2重襟・2重袖」ワイシャツを、カッコよく(?)
腕まくりする方法を、ご支援先の営業マンに、教えてもらいました。

モノマネさせていただきます!
パクらせていただきます。
どんなことでも、
真似することが、成長の近道。
ありがとうございます。
毎日、腕まくりするたび、古川さんのことを思い出します!
正式名称は「ミラノ風・腕まくり」だそうですが、
私は、「フルカワまくり」と、名づけています。
競輪選手みたい。(笑)
営業成績も「まくり」を発揮してくださいね!
2014年9月14日 22:36
参考までに、、、
そこそこ有名な友達のコンサルタントは、
東京・青山に、
他企業と共同で、電話受付等々をしてくれる
「レンタル・オフィス」を事務所にして、
コンサルタント商売をしています。
その彼、曰く・・・
会社案内とか名刺に「青山」という地名があるだけで、
以前よりも、明らかに仕事が増える・・・というのです。
「中西さんも、丸の内や青山に、
レンタルオフィスを借りれば、コンサル依頼が、増えますよ!」
こんなアドバイスを、してくれます。
・・・
これについては、私の主義には反しますので、その方法はとりませんし、
そんなことしなくても、仕事は、増える・・・
しかし、そのマーケティング手法は、素晴らしい!
このコンサルタント君の戦略は、
小売・サービス業の各社が、
銀座に店舗を構えるのと、同じ意味合いです。
「ユニクロが、銀座に出店しましたけど、成功すると思いますか?」
と、質問を受けることがあります。
単独店舗の採算としては、成功しない。
そう思います。
銀座の客層・品格・テイストと、
ユニクロのそれが、違い過ぎているからです。
しかし、、、
もしかすると、ユニクロの銀座店は、
単独店舗の採算としても、儲かることがあるかもしれません。
そのときは、
「銀座は、もはや銀座ではない。普通の街と同じだ」と、
言わざるを得ないでしょう。
日本における「銀座」とは、そうゆう立地です。
・・・
楽しい勉強会メンバーさんたちと、街を歩きながら、
そんな思索にふけるのでした。
「とても特別な、特長のある街」が、
あってもいいんじゃないか・・・と。
2014年9月10日 6:20
「中西さん、銀座のどこを見て、どんなことを感じているんですか?」
銀座でのミーティングを終えて、
参加メンバー同士で、懇親会会場へと、歩いていたときのこと、
こんな質問を受けました。
そんな質問をさせてしまうくらい、
興味津々・挙動不審な雰囲気を、身にまとっていたのかもしれません。
そのとき、私が感じていたのは「銀座」という土地の品位。
そして、
その品位をマーケティングに活かそうとしている小売・サービス企業の戦略です。
ざっと見たところ、
銀座に出店している店舗は、ほとんどが「赤字」と思われます。
家賃に見合うだけの売上が確保できている店舗は、
一部だけだという印象です。
他は、採算がとれていない店舗ばかりでしょう。
しかし、日本では「銀座に店舗を構えている」ということで、
信用が増し、品格の高い企業との評価を得ることができ、
他地域・他ルートでの販売に、良い影響を与えてくれるのです。
銀座に出店している企業は、
「銀座店」単独での「利益」が欲しくて、出店したのではなく、
「ブランドイメージを作ること」「他での販売を容易にすること」を目的として、
出店しているのです。
店舗の赤字分は「看板経費」と解釈して、
「銀座店」を作っている。そうゆうことです。
(後編に続く)
2014年9月2日 10:15
期待の若手コンサルタント・佐伯泰基・主催のセミナーにも、
たくさんの参加者が、集まります。

彼も、経営支援では、
私と同等か、それ以上に、現場での実績を上げています。
絵画の真贋を見抜く「優秀な画商」を育てるには、
生まれてから「本物」だけを、見続けさせることが、最も良い方法である。
以前の記事にも、このように書きました通りです。
http://sousai-keiei.com/nakanishi/blog/2013/06/16/
彼は、入社以来、
多くの繁盛葬儀社を、私のそばでコンサルティングし、
優秀な中小企業経営者と、接してきました。
ですから、
こんな場所に、こんなホールを建てる・・・とか、
当たるチラシ・看板の作り方・・・とか、
こんな組織と社員が、売上を作る・・・とか、
儲けている経営者の習性・・・とか。
普通の人が、ちょっと体験できない
「繁盛店の常識」が、すべての基準となっているのです。
2014年8月19日 21:58
人との出会いこそ、旅の思い出。
建物や、観光名所、うまい食事も、いいんだけけど、
旅の記憶に残っているのは、
そこでどんな人と出会い、どんな体験をしたのか・・・ということだ。
大学時代、バイク旅に出かけたときは、
北海道のライダーハウスのオーナーや、途中で出会ったバイク乗り、
競走馬牧場の人たちだったし、
社会人1年目・四国への一人旅で、
出会った酒販店のオッチャンが、
船井総研での初受注先となったことも、印象に残っている。
悪友5人で出かけたバリ旅行では、
プールで、水中バスケットボール勝負した地元のジゴロ・ワヤン一味。
・・・ワヤンたちの収入源は、日本人の女。。。
手帳にリストが、びーっしりでした!(トホホ)
松山では、尊敬できる2人に出会う。

一人目は、
「行列に並ぶこと」が、何より嫌いな私に、
1時間も待たせて、
イライラを最小限にとどめさせた
「道後温泉本館」の整理担当のおねーさん。
1) スマイリーな表情、
2) キビキビした行動、
3) お客様を気遣う言葉かけ、
4) 現在状況の適宜報告。
「何とか、早く入れてあげよう!」
「待ってもらって、本当にごめんね!」という気持ちが、伝わってくる。
接客の仕事って、まずは、
この1)~4)できればいいんだよねーと、とても勉強になる。
その動きを見ているだけで、
1時間、待っている値打ちがある。
温泉から出て行くとき、
わざわざお礼を言いに行きました・・・。
二人目は、
モーニングに立ち寄った、老舗喫茶店のオーナーさん。
タキシードに身を包み、颯爽と決まっている、
白髪交じりの、超かっこいいジーさん!
誰が相手でも、態度を変えることなく、
丁寧で優しい言葉づかいと、心配りで接してくれる。
その佇まいだけで絵になる。その存在そのものが、もはや「看板」。
「こんな大人になりたいな~」と
内面からにじみ出る雰囲気だけで、思わせるのは、
とっても凄いことだと思います!
松山に支援先を作って、
この喫茶店に通いたい。。。
2014年8月14日 21:04
オヤジの夏の友=高校野球。
はじまりましたね!

出場校の顔ぶれに、近年、ある特長があります。
それは「大学付属高校」が、増えてきていること。
ナニナニ大付属・・・という高校たち。
龍谷大平安、大垣日大、東海大相模、東海大四、健大高崎、盛岡大付属。。。
13校
名前から判断できない「大学の付属校」という場合もありますが、
そこは数えていません。
「少子化」という時代背景が、垣間見えます。
学校経営は、厳しくなっています。
大学の付属校になることで、生徒数が増え、経営が安定するのです。
ついでながら、、、大学付属校の野球部は、
受験のことを気にせず、野球に集中するから、強くもなるのか??
忙しいくせに、このブログを書くために・・・
歴代の甲子園出場校のなかの、大学付属校の数を数えてみました。
「マー君・田中将大VSハンカチ王子・斉藤祐樹」の時代は・・・
早稲田実業、駒大苫小牧に、東洋大姫路、文星芸大付、日大山形・・・・。。9校。
PL学園の桑田と清原の時代は・・・
東海大山形、立教、日大三、東農大二、東洋大姫路、国学院栃木・・・・。。8校。
兵庫県の野球少年たちのヒーロー・金村義明の報徳が優勝した年は・・・
早稲田実、国学院久我山、秋田経法大付、福岡大大濠。以上の4校。
怪物・江川が雨に泣き、達川の広島商業が優勝した年は・・・
日大山形、東洋大姫路、天理、日大一。以上の4校。
最後に野球マニアのうんちく・・・
野球の強豪校には、時代によって移り変わりがあります。
「・・・商業」の時代。
野球が強いのは、決まって「ナントカ商業」なんですよね!
高知商業、横浜商業、松山商業、宇部商業、銚子商業、広島商業、浜松商業、福井商業、。。。
次に来るのが「・・・学園・学院」時代。
野球に力を入れた私立高校が出てきます。
PL学園、報徳学園、常総学院、浦和学院、作新学院、智辯学園、尽誠学園、聖光学院。。。
これからは、いやもはや「・・・大付属」時代になっているのか?
高校野球マニアとしては、
ちょっと、寂しい気もするのですが。
これも「時流」というものなのか。
あー、
横浜商業のブルーのユニホームを、また甲子園で見てみたい!
2014年7月25日 11:06

大阪の面白い看板特集です。
今回ご紹介するのは、その名も「ブスの店」!!
ちょっと、一人では、行く勇気がないので・・・
大阪にお越しの際には、是非、ご一緒してください。
大阪市内で、出店調査の途中、また別の店がありました!!

・・・このネーミング意外と、繁盛するのかな??
チェーン店?
「ブス」の姉妹店??
ブスの語源について、調べてみました。
「附子(ぶし、ぶす)」が、言葉の由来です。
猛毒の植物・トリカブトの根のことだそうです。
漢方薬として使われるそうですが、
この処理方法を間違えて、口にすると、
顔の神経がマヒして、無表情になってしまうそうです。
つまり、マヒしたような無表情のことを、そもそも「ブス」と言う。
思い当たること、ありますよねー。
男も、女も同じです。
結論!
笑顔にブスなし。
笑えば、誰でも美しい。
表情豊かに、ニコニコしている人に「ブス」はいない。
2014年7月17日 14:17
隠れ家酒場で、ご飯を食べる。。。
酒は飲まずに、ノンアルコール・果物飲料を飲む。

コートのポケットに、
ウイスキーの小瓶を忍ばせ、
グビッと、飲み干しながら、コンサルティング・・・。
そんな破天荒なコンサルタントに憧れるのですが、
自分には、どうもできません。
今日は、「酔いどれ・気分」の
どうでもいい経営談義に、お付き合いくださいませ。
「いい人が、良心的な葬儀をしている」
そんな葬儀社の売上が、意外と少ない。
「悪いヤツが、ボッタクリ葬儀をしている」
そんな葬儀社の売上のほうが、勝っている。。。
これは、
葬祭業界に限らず、
他の業界でも、よくある話。
なぜ、そうなるのか?
その理由を、ナナメから切ってみたいと思います。
売上とは、
第一に、経営者の「戦略」。
第二が、顧客の「満足」。
お客様の「満足」が、最初にあるのではなく、
経営者の「戦略」が、最初にある理由。
それは、
お客様からの「初回注文」を如何に得るか?
ということに関しては、
商品の「満足度」とは、無関係だからです。
たとえば、
いくら味の良い飲食店でも、
まず「お店に入ってみよう」と感じてもらわなければ、
「美味しかった!」という「満足」は、発生しないのです。
ですから、
お客様との「ファースト・コンタクト=初めての接触」に限って言えば、
経営者が作った「戦略性」にかかっていて、
「商品内容」とは、関係がないと言えるのです。
どこにホールを作るのか?
どんな特長のホールにするのか?
どんな葬儀を提供するのか?
他社と差別化要素を、何に設定するのか?
どんな販促・営業手段で、会員を集めるのか?
これが「戦略」です。
「戦略とは、会社が儲かる方向を決めること」
では、提供する商品が悪くても、売上は成立するのか??
商品に対する「満足度」は、
「リピート注文があるか、ないか」と比例します。
商品に、お客様が満足すれば、リピート注文が入ってきます。
そして、リピート注文が多いほど、売上=経営は安定します。
リピートの少ない会社は、常に危険がつきまといます。
流行っていたのに、すぐに潰れてしまう会社や、お店には、
「リピート注文」が、入っていなかった。という原因があります。
売上とは、
「初回注文」を、如何に増やすか =戦略性
「リピート注文」を、如何に増やすか =商品満足度
この2つの要素からできているのです。
2014年7月10日 19:02
野球つながりで、
記憶にとどめておきたい話を、ひとつ。
巨人軍監督・原辰徳さんの父・原貢(みつぐ)氏が、
先日、逝去されました。
「三池工業」
夏の甲子園・歴代優勝校のなかに、耳慣れない高校の名前あります。
昭和40年のことです。
実は、この高校こそ、原貢氏(当時31歳)が、監督として率いた高校です。
炭鉱の町の公立の無名校を、全国優勝にまで導いたのです。
その後、実績を買われ、
無名であった東海大相模高校の監督として、迎え入れられ、
甲子園出場に導き、再び全国優勝を成し遂げる。

その後、息子・原辰徳が、同校に入学すると、
非常に厳しく、鍛えたことは、有名です。
辰徳への1000本ノックは、特に熾烈を極めたといわれ、
他の野球部員を引き締めるための、見せしめとして、
中心選手であった息子を拳骨で殴る、倒れれば、蹴るということもあったそうだ。
教え子たちへの言葉も、多い。
「今、スタメンであることは、重要じゃない。花が咲く時期は、選手によってマチマチだ。」
「チャンスに、打てる打者こそ、良い選手。」
「野球も人生も、絶対に逃げちゃ駄目だ。」
「結果の為には、過程が大事。だから、日頃から一生懸命、練習しなさい」
「お前もつらかっただろうが、俺もきつかった」
これが、原辰徳の高校生活・最後の試合に負けたときに、かけた言葉。
原辰徳は、現役を退いたのち、監督となり、
巨人を強くし、日本代表監督としても、世界一に。
監督としてのDNAも環境も、素晴らしいものがあるのだろう。
さて、経営の話。
原貢ほどのレベルで、後継者に接している経営者は、
どのくらい存在しているのだろうか?
息子を、社員以上に、甘やかしていることはないだろうか?
また、原辰徳のように、
父親のシゴキに耐えられる後継者は、存在しているのだろうか?
実家だからと、
普通の会社に勤めている以上に、甘えていることはないだろうか?
父も子も、能力のあることを「親子鷹」という。
そのような親子経営者を知っているが、
そうでない同族経営の会社も、実際のところ多いものです。
育てる側の覚悟、育てられる側の覚悟。
夏の高校野球が始まる季節、ふとこのようなことを考えるのです。
2014年6月22日 9:24
台風が来て、街路樹が倒れた。
なぜ、街路樹は、倒れてしまったのか?
「強い風が吹いたから」・・・これは、「契機=きっかけ」。
「根が腐っていたから」・・・これが「真因=本当の理由」。
契機と真因は、
よくちゃまぜになって、会話されています。
仕事の会話をするときに、
ここを混同すれば、噛みあいません。
たとえば「お客様アンケート」の
「なぜ、当社を選んでいただいたのですか?」という設問への、
回答にも、「契機」と「真因」が、入り乱れています。
「チラシが入っていたから」
「事前相談をしていたから」
「価格が明瞭と聞いていたから」
「以前、参列したことがあったから」
「会員だったから」等々・・・。
契機と真因を、明確に整理して、お客様の声を聞くことが、
その会社に応じた、優れた戦略・戦術を作るための原動力となります
自分を取り巻く出来事に関して
いつも、曖昧にしないことが大切なのです。
「契機」も「真因」も、両方が大切。
でも、何度も同じ失敗が起こり、
成長できない会社や人には、
どちらかと言えば、「真因」を探ろうとする習慣がありません。
その現象の理由を「きっかけ=契機」だけで、
見ていることが多いように感じます。
根っこに横たわっている真の理由は、なんだったのか?
それは「契機」なのか「真因」なのか?
「どうしてそうなったのか?」を、少なくとも三度は、
自分と他人に問いかけ、真因を追究してみましょう。
2014年6月15日 20:40
サッカー、ワールドカップが開幕しましたね!
初戦のコートジボワール戦、惜しかったです。
個人的に注目しているのは、ニッポン代表なら、やっぱり本田選手。
最初「生意気なヤツだなー」「あ、サッカー選手のパターンね」なんて思っていたけど、
知れば知るほど、なんだか親近感が持てるんですよね。
実は、泥臭くて、とても真面目!
必ずしも「センスがある」とは、
言えなかったサッカー少年が、夢に向かって努力を重ね、
プロになり、海外でプレイすることだけに満足せず、
ワールドカップ優勝を「本気」で目指している。。。
そんな彼を見ていると、
「自分もできるんだー」「やらなきゃなんねー」という気持ちになれます。
もちろん、彼みたいに「有言」じゃなくても、
「無言」で、大きな目標に向かって、
頑張っている選手や社会人も、たくさんいるけど。
「コイツ、めっちゃ面白いやん!」
「本気だな!!」と思った、ワールドカップ出場決定会見です。
12分手前から見れば大丈夫!先輩への「ダメだし」・・・。
各人へのハッパは、
「みんな1年間で、自分を磨いて、また集まろう!」の熱きメッセージ。
分度器の角度を「夢の持ち方」とするならば、
本田選手は、90度に限りなく近い角度(=ワールドカップ優勝)に設定して、
365日・24時間のすべてをそこにあわせて、生活してきたんだろうな・・・。
結果、80度くらいに終わってしまうかもしれない。
でも、最初から30度くらいにあわせているよりも、ずっと大きく成長している。
それに、最初は、小さな開き(Y軸・コサイン)しかないかもしれないけれども、
時間(X軸・サイン)が経てばたつほど、その開きは、大きくなる。
サイン・コサイン・タンジェント・・・三角比の理屈。
「心の分度器」を、どの角度に設定しているのか??
そんなことが、とても勉強になります。
・・・本田選手やイチロー選手が、小学生時代に書いた作文は有名ですよね。
早速、自分の小学生時代の文集を、読み返してみました・・・
・・・「ダメだ、こりゃ」・・・・
としか、言いようがありません。
いやいや、今からでも間に合う!
2014年6月12日 22:27

先日、退職したスタッフが、
「最後のあいさつに・・・」と、作ってもってきてくれたチーズケーキです。
彼女は、自分の夢を追いかけるために、
当社でアルバイトしながら、エステの勉強をしていました。
晴れてエステ・スクールを卒業することができたので、
このたび当社を退社し、エステ系の仕事に就くことになったのです。
「ウチは、入ったら、やめられへん会社やで!」と、
無理を言って、ずーっと引き留めていましたが、
さすがに、もうこれ以上、引き留める訳にはいきません。
後任が決まるまで、次の仕事探しも我慢して、
当社で、つとめてくれました。
ありがとう!
思えば・・・、
こうして、辞めたあとで、
わざわざ挨拶に来てくれる子は、これまで、少なかった。
もちろん、彼女の資質もあるのでしょうが、
彼女の周りのスタッフのみんなと、
幹部として頑張ってくれる「アネゴちゃん」たちのレベルが、
以前とは、段違いに、優秀で会社想いのモデルとなる人材だから、
こうゆう現象が起こるんだろうな。
本当に、そう思います。
(だって、俺は、何にも変わってないもん。。。)
幹部・スタッフが、頑張ってくれているな、恵まれているんだなー。
と、こんな現象で、改めて実感します。
エステちゃんは、1年間、しっかり勉強してから、
うちに帰ってきて、エステ部門を作るように。
日本最強のコンサル会社が、プロデュースする直営エステ店を作る!
道は分かれても、まだひとつの道に戻る。
同じ方向を向き、真面目で明るく働いてくれているスタッフのみんなが、
じいさん、ばあさんになっても、
ずっと安定的に、安心して、お金の不安なく働ける場を作る・・・・
真剣にそんなことを考えながら、経営しています。
佐伯の雄姿を、ニヤニヤ目に焼き付けて、帰ってゆきました。

!
チーズケーキ、とても美味しかったです!
(俺の分だけ、毒入り・・・とかじゃなくて、良かったー)
2014年5月29日 7:28
関東地方のご支援先にて。
新規に作った「家族葬ホール」の広告物作成のための写真撮影に、立ち会いました。

どんなことをPRしてゆきたいのか?によって、
どんな写真を撮れば良いのか?
内容が変わってゆきます。
「小さいこと」をPRしたいのか?
逆に「大きいこと」をPRしたいのか?
「あたたかさ」をPRしたいのか?
「スタイリッシュ」をPRしたいのか?
それによって、撮る写真の角度や光の入れ方、
インテリア・小道具の置き方、画像調整の方法・・・等々を、変えています。
目的に応じて、それを表現できる写真が撮れると、
チラシ、ホームページ、カタログ等々を作成するときに、
とても役立ちます。
「今、中西さんが、撮ってる感じの写真を撮ってくださいね!」と、
私の意見を尊重して、広告会社さんに、指示を出してくれる社長さん。
「もうちょっと、こんな感じに配置してみませんか?」という
私のわがままな要望に、汗をかきかき、椅子や祭壇、小道具等々を、
持ってきて、並び替えてくれる、この葬儀社のスタッフさん。
料理屋さん、花屋さんのご協力からも、
普段の社長の熱心な仕事ぶりを、うかがい知ることができます。
みんなの気持ちが、ひとつになり、
大繁盛の予感ビンビンの「家族葬ホール」が完成しつつあります。
男・意気に感じ仕事できることに、感謝です。
何としても、成功させます!
このスタイルの家族葬ホール、
相当の「高回転」実績がありますので、きっと大丈夫だと思いますが。。。
2014年5月25日 22:00
京都市内で、
出店候補地を物色中に・・・。
歴史ある、ワタシ好みの建物を発見しました!
看板を、よーく見れば・・・
おぉ、「任天堂」と書いてあります。

ファミコンやゲームボーイ、DS、Wiiなどなど、
テレビゲーム関連の商品が主力の「任天堂」の本社のようです。
看板にある通り「任天堂」は、
元々は、花札・かるた・トランプ等を作る会社でした。
創業から100年以上の歴史がある会社です。
「社是・社訓は、作らない。時代に対応するために」
「経済界への政治的活動は、行わない」
「多角化失敗の歴史から、異業種進出は、行わない」
こんな方針があることでも、有名です。
新しいものを生み出し「変わってゆくこと」こそが、
企業の生き残りの条件であることを、改めて実感しました。
「進化論」のダーウィンが、
残したと言われている名言を、思い出します。
強い者が生き残るのではない、
賢い者が生き残るのでもない、
唯一、生き残ることができる者、それは変化できる者である。
2014年5月13日 23:53

コンサルティングで、北海道をご訪問させていただいたとき、
北海道大学のキャンパスが、キレイに見えました。
ここの初代教頭は、「少年よ、大志を抱け」の言葉が有名なクラーク博士。
“Boys, be ambitious!”
生徒たちとの別れの際、この言葉を残し、馬に乗り走り去って行った・・・という、
心が熱くなる風景と言葉が、有名な伝説です。
クラーク博士の名言に、もうひとつ、あまり知られていないけれども、
個人的に、大好きなものがあります。
“Be gentleman!”
「紳士であれ」というセリフ。
北海道大学(当時:札幌農学校)の開校の際、
北海道開拓使長官・黒田清隆より「校則を定めましょう」と相談を受けたとき、
クラーク博士は
「ここに、校則はいらない。〝紳士であれ〟これひとつで、十分だ」と、言ったそうです。
細かなルールを定めるのではなく、
何が良くて、何が良くないのか・・・、それを、自己判断しなさい。というもの。
「自由」と「責任」は、同じ。
ある意味、こちらのほうが、厳しいのです。
私個人は、どうでもいいルールに縛られるのが、とっても、嫌だ。。
だから、他の人も、そんなことで、縛りたくない。
原理原則に、基づき、自分の責任で行動する。
そんな組織で、動いてゆくのが、理想だから、、、
できるところまで、これでやってゆきたいと思います!
2014年5月10日 14:23
哲学を、わかりやすく仕事に活かしましょう!
「弁証法」という哲学です。
Aという主張と、
Bという主張が、食い違う。
ここで、論議して、
そのベースにある本質が残ったCという策が出てくる。
これを「らせん的発展」「生成する第三項」と呼んでいます。
AがBを否定するのみ・・・そんなことで、発展はない。
BもAを否定するのみ・・・それでも、発展はない。
では、
AとBの真ん中をとろう・・・薄くなって、良策が生まれることが少ない。
良い仕事をするためには、
AもBも「相手の真の意図」を受け入れ、
両方の根底の本質が同じで、しかし別物の、さらに良質なCを生み出そうとする。
こうゆう考え方・思考回路は、
商売繁盛・人生繁盛の基本であると、信じています。
これは、ドイツの哲学者ヘーゼルが提唱している
「弁証法論理学」というもの。
A=テーゼ(命題・正)としたとき、
B=アンチテーゼ(反対命題・反)となる。
C=ジンテーゼ(統合命題・合)である。
「対立や否定」こそが、次への発展へのきっかけとなるように、
いつも考えてゆく習慣が大切なのです。
これを、日本語で言えば、止揚(しよう)
=ドイツ語では「aufheben、アウフヘーベン」という言葉で表現される、耳慣れない言葉です。
「否定する・棄てる」という意味と
「保存する・高める」という、ふたつの意味がある言葉なのです。
つまり、AもBも、
否定され、まったく別の新しいモノが、出てくるとき、
その全てが、捨てられるのでなく、
A・Bの中身のうちで、積極的要素が、新しく高いレベルのCへと発展する。。。
こうゆうことです。
彼が、ハーゲル。

あ、ヘーゲルでした。
2014年5月8日 8:16
天王寺近辺には、
楽しい人生の先輩たちが、たくさん集まっています。
商店街のなかには、
いつも満員の将棋と囲碁の「道場」があります。
この注目度のなかで、勝負師たちが、腕を競いあう・・・。

そして、ここでは、
「ゆず」みたいな、じーさんユニットが、リクエストに応えながら、
懐メロを大声で歌い上げる・・・。

だいたい、歳をとったら、
男は元気がなくなり、女はどんどん元気になってゆく。
男は、コミュニケーションをとるのが、下手くそだ。。。
デイサービスに集う年配者をみてても、
女はみんなでワイワイやってるけど、男は一人でジトーッとテレビみたりしてる。
ここ、天王寺(新世界)のじーさんたちは、別。
「ジジイ」がみんなで、青春に戻れる街なんだろうなー。と思います。
私が、本能的に惹かれてしまうのは、
もしかして、そんなところに、理由があるんじゃないかな。
大阪にお越しの時には、是非、この素敵な街を散策してみてくださいませ。
2014年5月4日 20:02
ゴールデンウィーク中、
かねてより「見て欲しい」と
依頼を受けていた新店候補物件を、ようやく見に行くことができました。
世間様は、みんな休んでいるみたいなのに、
働いているのは、なんだか、しゃくにさわるので・・・。
乗換えを活用して、街をブラブラ歩きしました。
下車したのは、ディープな大阪を象徴する街・天王寺。
スカイツリーよりも、やっぱり「通天閣」が好きやねん!!

「ソースの2度づけお断り」は、大阪の串カツ屋で有名ですが、
こんな大きな看板を出しているのは、初めてみました。
「マイナス・フレーズ」なのに、店は満席です!

でも、観光客相手なら、このくらいの大胆さが、
集客には、効果があるのかもしれませんね。