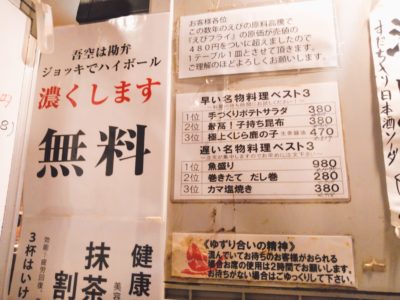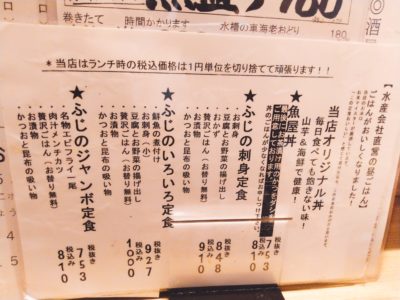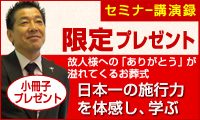2025年6月21日 19:11
2025年3月から新幹線「のぞみ」の自由席車両が、
3両から2両に削減されました。
出張の移動は、基本的に「自由席」を好みます。
何事も「自己判断の領域」が多いほうを選びます。
だから、3月以降「のぞみ」はちょっと大変です。
自由席を好む、根本的な理由は、
クライアント先での打ち合わせ時間が、延びることがあるからです。
もうひとつの理由は、
隣に変な乗客がいたら、すぐに、移動できるからです。
指定席は、自分の座りたい席を指定はできますが、
近くに、どんな乗客がいるか?という点に関しては、
移動手段の主体である鉄道会社や航空会社に、決定権があります。
席を確保する安心よりも
指定の席のご近所が誰か?そのリスク回避のほうが、優先順位が高いのです。
たとえば、
下記のような乗客がいたとき、一人でサッサと避難できるのが、
自由席のメリットです。
(20~30回に1回くらいしか、当たりませんが)
・スマホビデオ通話、イヤホンなしでyoutubeを観る=主に、中国人
・会話の声がデカい。=主に、おばさん
・強烈な臭い(香水、体臭、たばこ、食事)
・占領地域。股を広げて座る肥満オヤジ、ひじ掛けを占領する肥満オヤジ。
=肥満の人間は、態度までもデカイ。その性質が肥満体を作のである。。

(手前のワイシャツまくり腕=私です・・・、ひどくないですか?)
・なぜか美顔器を、ぶぃーーんと、やり続けるオヤジ

(髭剃りか??と思いきや、美顔器でした)
・リクライニングをフルに後ろに倒して、くっついて寝るバカップル。

余談・・・・
人前でイチャイチャするカップルは、9分9厘、ブサイクな2人である。
美男美女が、イチャイチャしてるのを、見たことがない。※欧米系外国人を除く
いつも、ビミヨーーーな2人が、人前でイチャイチャする。
めったにできなかった、彼氏・彼女ができたことが、嬉しいのか、見て欲しいのか。
自分を社会のなかで相対化できていない。
できていたかもしれないが、(彼女彼氏ができた)ことで、それが崩れた。
恋愛に慣れてないと、だいたい、こうなる。
鉄道&航空会社さんへ
指定でもいいんだけどさ、、
「ここに指定をとってるのは、185cm・ヒゲの大男だよ」って、
わかるようにしておいてもらえれば、避けてくれる。避けられる。
指定席の予約システムに、身長体重を登録しておいて、
カテゴリー色分けしておくのが良い(もちろん任意で表示)と思いますが。。どうでしょう?
2024年11月24日 19:14
盛岡から宮古へのルート。
花巻・北上から、釜石へのルート。
岩手県内陸の中心地と、沿岸部の街まで。
以前は、
車で、峠道や川沿いの道を、3時間以上かけて、移動しなければなりませんでした。
そこに、震災復興を名目に、大量の資金が投入されて、
無料の高速道が敷かれました。
今や、最速45分。普通に走っても1時間程度で、沿岸部に到着できます。

道中~沿岸の街は、工事中は景気が良く潤う。
工事終了後、生活も便利になる。
しかし、
それは、一時的なものです。
何も手を打たなければ、
これらの街の衰退が、一気に始まります。
泊りじゃなきゃ、行けなかった沿岸の街・宮古や釜石にも、
日帰りで行くことができるようになる。
すると、地元で泊まって、ご飯を食べて、飲んで・・・という「お金が」落ちない。
営業所・出張所を設けていた会社も、内陸の営業所と統合する。
出張で対応できるでしょう。と。
大きな会社の給料の良い企業人の人口が減る。お金が地元に落ちない。
沿岸部の若者は、簡単に流出する。
盛岡に住むことへの抵抗感がなくなる。
「車で1時間だから、すぐ帰ってこれるよ」と。
病院も、田舎にベッド=入院施設は必要なくなり、都会に集中するようになる。
交通の大動脈の開通=つまり、時間の短縮・利便性は、
「一番」への一極集中をもたらす。
これまでは、「不便であること」が、経済競争を避けるバリアとなり、
均衡を保つことができていたのである。
・・・・・
途中の街は、もっと深刻になる。
高速がなかった時代は、
「遠野」あたりで、寄り道するかー。
昔の民家とか、カッパの出る小川とか、田んぼとか、見ていこう。
どれ、民宿で、1泊しようか。。とか。
偶然、見つけたお洒落なカフェを見つけて、ご満悦。
展望台に上がって、
そこで会う人に、美味しいお店や、
面白いスポットを聞いて、行ってみる。とか。そうゆう行動をとっていました。
人が滞留する時間が長ければ、その分、経済も成り立つ。
しかし、今は「高速道の通り道」の街。
時速100kmで、びゅん!!と通り過ぎてしまう。
長野と東京に新幹線が開通したときも、そうだった。
長野は、一時的に、潤うけれども、長期的にはマイナスとなる。
「○○開通・祝賀式典」などとやってても、
何も、めでたくはない。大危機のはじまりだ。
と、本当のことを言うと、地元の人に怒られた・笑
でも、現実は、これから「一番」が潤う(=吸い取る)だけである。
便利になるのは良い事だけど、
来たる未来に備えて、官民一体となり、
その街の「一番」を創出しておかなければならない。
道路作って、鉄道作って、満足している場合じゃない。
ちょっとマーケティング的なことも、書いてみました。
2023年4月2日 19:14
今年、桜が、
なぜか、一段とキレイに見えます。

あと何回、桜が見れるだろう。
とか、思う日がくるのかな?
それに、亡くなった方を思い出すのも、桜。である。
そうゆうことは、
勝手にこちらが「イメージ」で、
紐づけているだけで、、
桜は、桜で、
頑張って生きているわけですが。
お年寄りが「桜好き」な理由が、
なんとなく、わかるようになってきた春です。
2021年6月20日 21:28
コロナ前には、行列ができているから、敬遠していたお店。
その大繁盛店も(さすがに、今は、暇だろう・・・)と、狙い撃ちで、回ることが、
コロナ禍のプライベートの楽しみのひとつとなっている。
※代償は、お腹のお肉である・・・笑
う、うまい、、お値打ち・海鮮丼。。

素材の良さ&ボリュームは、もちろんのこと、、
具材とご飯の間に、絶妙の量と質で「天かす」が入っています。
他にはない見事な食感を、作り出す。
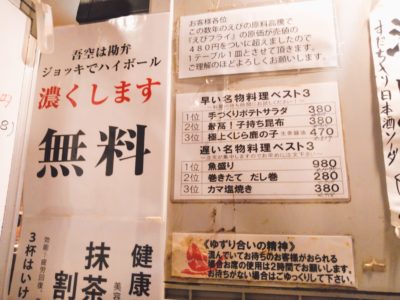
このPOP類も、また、秀逸で。。
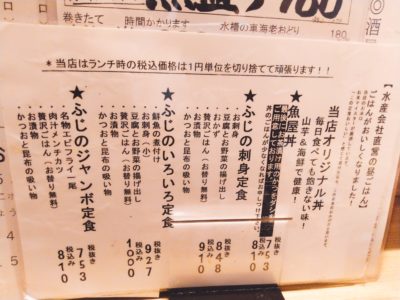
商品にも、販促にも、
ズドン!という本質部分(素材・価格・サービス)の良さに、
ひと手間、ひと工夫。が入っている。
2021年3月27日 22:02
試験の全日程が、終了した日の夜、
「受験勉強、終戦、おつかれさま。
全体を通して、どうやった?」と、彼にラインしたら、
「人生、1番の敗北を経験したことが、1番の収穫」と、返ってきました。
私立大学3連勝のあと、
準備万端で臨んだ、国公立大学・前期試験での不合格の結果のことを
率直に受け止め、「収穫」と、言ってきました!涙
その言葉を、本音で言える人間に成長できたことは、
どんな大学に合格するよりも、価値があるぞ!
俺は、そっちのほうが、はるかに嬉しい。
・・・「やることは全部やったから、悔いなし」くらいのことは、
言ってくるヤツだと思っていたが、その想像を超えていたな・・・
1敗から学ぶことは、
100勝から学ぶことよりも、深く、大きい。
世の中には「1敗」を経験したことを、
現在の成功の礎にしている人が、たくさんいる。
そして、「100勝」=順調に勝ち続けていたのに、
現在の停滞、没落を余儀なくされている人も、存在している。
また、「1敗」から、何も学ばない人が、
世の中の大多数である。
で、キミは
何を「収穫」したんだ??
聞かせてもらおうか!!
あと、もう少しの間だけ「コンサルティング」させて欲しい。
ヒヨコくんも、
大空を飛べるようになったんだ!!笑

最終的には、
後期試験で、第一志望「崖っぷち」合格をつかんでいました。
気にかけていただいた皆さんからの「愛」も、
しっかり伝え、受け止め、力となっています。感謝です。
2019年3月31日 20:57
歴史話が、最近、多い。
ついでに、もうひとつだけ。
以下、どんな家来が合戦に強いか?と聞かれたときの
ある戦国大名の答えです。
勇猛が自慢の男など、いざというとき、どれほど役に立つか疑問である。
名誉を欲しがり、派手な場面では勇猛ぶりを見せるかもしれないが、
いくさの中で、派手な場面は、ごく一部である。
他の場所では、身を惜しんで逃げるかもしれない。
見せ場だけを考えている豪傑は、ほしくない。
戦場で本当に強いのは、まじめなものである。
たとえ、非力であっても、責任感が強く、
退くなと言われれば、骨になっても、退かない者が、多ければ多いほど、
その家は強い。
合戦で、勝ちに導く者は、そうゆう者たちである。
誰にとっても「怖い」という自然な感情を抑え、
仕事させるものは、義務感である。
人間が、動物と異なり高貴である点は、理性であり、義務感である。
みなさんの会社には、
そうゆうスタッフが、どのくらいいますか?増えていますか?減っていますか?
そうゆうスタッフに、目を向けていますか?
2018年4月15日 21:05
最近、経営関係以外の勉強をする時間が、増えてきました。
知ったことを、書き留めておきたい。
ネズミは、たくさん生まれ、
ゾウは、数年に1度生まれるのは、なぜか?
見た目の話だけで言えば、体の大小でしょうが、
根源的な生物学的な観点から言えば、
それは、カロリー配分の問題にあるそうです。
ネズミ=繁殖(すぐに死ぬ、小動物)
ゾウ=修復(長生きする、大型化)
自分のカロリー配分を、
繁殖に重きを置くか、修復に重きを置くか。
ふと、
企業のことを考える、
カロリー配分とは、利益と意識の配分のことだろう。
繁殖=ハイペースで出店。すぐ閉店する。小型店。
修復=リフォームする。長く続ける。大型店。
繁殖=どんどんスタッフ・取引先を増やす。すぐ辞めても大丈夫。小モノ。
修復=少数のスタッフ・取引先を育成する。長続きする。大モノ。
・・・
なるほど、カロリー配分ですね。
2018年3月4日 21:36
「●●、これじゃ、ダメだろー!!」
社長を呼び捨てにして、バシッとダメ出しするのは、
社長のお母さま。
クリーニング会社のご支援先でのひとコマ。
夕方、工場の仕事を終えて、事務所に顔を出す。
いつも肩にタオルを巻いている。
全力で仕事してきた感が、全身から沸き立つ。
髪は、短髪。チーター(水前寺清子)のような。
「なに、言ってんだ!!これはこうゆう意味でやってんだよ!」
息子である社長も、負けずにやり返す。
目の前で、数分間、激しい言葉が飛び交う。
「そうかい、じゃあもう、好きにしな!」
この親子バトルは、
いつも決まって、お母さまの、この言葉で終わる。
驚くことが、いくつかある。
この言葉を発したあとは、まったく何もなかったかのように
ごく普通の会話に戻る。
あれだけ罵倒しあっていたのに、お互い、ジトジトあとを引かない。
カラッとして、今までの喧嘩が、嘘のような平常に戻る。
そして、
言いたいことを言って
「好きにしな!」と言ったあとは、本当に、好きにさせる。
息子も、母親の言うことを、少し勘案しながら、施策を決めている。
最後に、
暴風雨のような親子は、バトル中も、そばにいる私を、絶対に巻き込まない。
「ねえ、中西さん」とか「中西さんは、どう思う」とか、
「だいたい、アンタがついていながら・・・」とか、一切ない。
仲裁の必要なく、完結させる。
まして、1対1を、2対1にしよう・・なんて気は毛頭ない。
私には「すみませんねー」と言いながら、やりあっている。
場所は、群馬。
「上州名物・かかあ天下と空っ風」という有名な言葉がある。
養蚕で栄えた群馬では、勤勉で働き者の女性が多く、発言権も強かった。
からっ風とは、激しく、乾いた「赤城おろし」。
吹き荒れるのは日中の一時で、夕暮れには、止んでしまう。そして晴天をもたらす。
まさに、この言葉の通り、上州名物の親子喧嘩だった。
お母さまの訃報。
同じ地域にある、ご支援先の葬儀社さまから、
ご連絡いただき、知ることとなりました。
ご冥福をお祈りします。
もう、この素敵な「上州名物」を目にすることはできない。
でも、私たちの胸のなかに、学ばせていただいたことが、生き続けている。
2017年7月6日 21:31

1ヵ月ほど前の新聞記事より。。
葬祭業界でも、ここ数年、どんどん増えています。
本当に、様々な理由で。
「業績が悪いから」という理由だけではないのが、最近の特徴。
「いざ!」というときに、動けるように。
もし、進出されてきたら、逆襲できるように。。
売上・利益を上げて、準備しておきたいmのです。
2015年10月25日 11:08

愛知県のクライアント先からの帰り・・・
名物のきしめんを食べながら、、、先日のブログの続き。
ちなみに、私は、大学卒業後、
経営コンサルティング会社・船井総合研究所に就職し、
売上アップ支援の現場に入りました。
以降20年間、勤務時間外も、ほぼ全ての自由時間は、
「売上アップ支援の仕事」という「チャンネル」に設定して、生きています。
1日のほぼ全ての時間をそれに使い、
土日も半日は仕事を行い、
コンサルタントとしての力を証明するため、自分で店舗経営も行い、
数えきれないほどの社長・幹部の方々と、本気の打ち合わせをさせていただいています。
やっと最近、この分野に関する能力が、
人よりも、異常なくらい発達していることを、自覚してきました。
最初から、特別な能力があったとは、とても思えません。
ただ、
「僕に依頼してもらえれば、
絶対に売上を上げることができるコンサルタントになりたい!」
「プロフェッショナルになりたい!」と、強く願っていた普通のアンチャンでした。
そうゆう人間が、物理的に、その「チャンネル」=環境に、
身を置いている時間が、長かっただけです。
全人類に、等しく与えられた24時間のなかで、
どの「チャンネル」にあわせて、生きるのか??
人それぞれ、どんなテーマでも、かまわないと思います。
ひとつだけ、条件があるならば、
その最終テーマの人生を、誰かの責任にしないこと!!
自分が選んだ「チャンネル」の通りの人生になっているだけだから。
「なりたい自分」のイメージとマッチした、
「チャンネル」にあわせることができているのか?
そこに身を置いているのか?
そこが、大事なんだと思います。
2015年9月4日 21:35
東京オリンピックのエンブレム問題。。。
結局、使用中止。
新しく公募することになりましたね。
先日の「祝勝会」での一コマ。
クライアント先社長の
ご友人であるカメラマンの言葉に、とても、感銘を受けました。
オリンピック・エンブレムのパクリ問題について、
話題が及んだときの彼の返答。
「パクッた、パクってないの問題よりも、
あのエンブレムが、ダサいことが、大問題だよ」
そうか!
それだ、自分のなかでも、何か引っかかっていたことは!
さすが、
一線で活躍しているプロは違う。
こうゆう、本質をズバッと、
一言で、相手の何かを撃ち抜くことのできる人になりたいものです。
2015年3月10日 22:42
セブンイレブンが、他のコンビニと比較して、
日販(1日当たり売上)で、10万円以上も勝っているという事実。
新聞公表のデータによる計算だと、その差20万円!
そして、
消費税8%後も、売上を伸ばしているという事実。
その理由は、どこにあるのか?
セブンカフェがあるから?
セブン銀行ATMがあるから?
PB(プライベートブランド)商品が多いから?
本を受け取れるから?
ドーナツの販売まで始めたから?
鈴木敏文会長のカリスマ性?
私は、創業以来、息づく「単品管理」の思考回路。
つまり、「商品力」こそ、その根本理由である、と考えています。
30坪~40坪という、狭い店舗スペースのなかで、
売上を最大にするためになされている、数多くの工夫・仕掛け。
なぜ、この1アイテムの商品が売れたのか?
もっと売るためには、どうすれば良いか??
その「仮説(現場を変える)と検証(数字の動き)」の繰り返し。
小売業のマーケティングの基本を、
現場で積み重ねる思考回路が、根底にあり、
上の方(氷山の一角)が見えているに過ぎません。
根底を飛び越えて、
「徹底した顧客志向」だとか「新商品・新サービスの投入」だとか、見える部分だけを、
繁盛のポイントとして、とらえてしまうのは、
「上っ面を、撫でているだけ」ということに、なりかねません。
セブンイレブンについて書かれた書籍は、たくさんあります。
そのなかでも、もはや、この本を見つけるだけで、
至極の「ノウハウ」である、誰にも教えたくない!!とも言える、名著があります。
あまり売れてはいませんが・・・
良い本と、売れる本は、別なんです(笑)
興味のある方には、ご紹介しますので、また聞いてくださいネ!
2014年9月17日 10:07
客数アップの生命線は、「安い商品」です。
御社はどう位置付けていますか?
先日、支援先をご訪問するために、北海道に行きました。
北海道には、数多くの有名お菓子メーカーがあります。
そのなかでも、有名な企業「六花亭」の店舗に、
「シュークリーム85円」の大きな看板が貼りだされていました。

これは、マーケティングの原則通り!
客数を上げるための「集客商品」を、戦略的に位置づけています。
「その会社のなかで、最も安い商品=集客商品を、PRすること」
そして、「その集客商品が、他よりも、やや優れていること」
これが、客数を上げるための最も効果的な「商品戦略」です。
数多く売れるということは、それだけ、たくさんのお客様が体験する商品です。
「安い」ということは、「買いやすい」商品です。
つまり、その店を利用する「きっかけ」となる商品であり、
新規顧客がたくさん来店してくれるようになります。
お客様が、たくさん来店すれば、
本来、売りたい商品(儲かる商品)を、売るチャンスも増えます。
「安い商品だから、仕方ない・・・」と、手を抜いて仕上げては、ダメなのです。
「安くて儲からないから、看板に出さない」
これでは、客数が上がるはずがないのです。
地域の中で一番、「仏壇」を数多く売っている「仏壇店」は、
「線香・念珠」を地域で一番数多く売っています。
地域一番の園芸店は、「鉢物」を売る前に、
「球根・苗」を、たくさん売ります。
地域一番の車整備工場は、「車検」を売る前に、
「オイル交換」「キズ修理」をたくさん売ります。
北海道の大学生の就職希望ランキングで、
常に上位に食い込む企業である六花亭ですら、
このように地道かつ丁寧に「最低価格商品」を、品揃えし、PRしているのです。
これだけの有名企業でありながら、他社よりも、安い価格を打ち出しています。
「最低価格商品」に対する「王道」を実践することに関して、
葬祭業界も、学ぶべき点が、たくさんあるのではないでしょうか。
2013年11月13日 22:03
「儲かっている会社」と、ひとことで言っても、
その立地や規模、業種、業態、地域性により、色々にカテゴリ分けされ、
いくつかだけの良い点をピックアップして、それを他店にあてはめることはできません。
そのなかでも、必ず共通しているもの、
根底部分の本質では、完全に同じものを「繁盛店の共通点」として、まとめてみました。
①お客様から見えない部分では、とにかく節約、節約!
しかし、お客様から見える部分には、コストを惜しまない。
②設備や什器、施設などは、トコトンまで使い切る。
「使えなくなったら、新しくすれば良い」「確実に儲けて利益が出そうなら、大きくすれば良い」という考え方である。
③他人の金を借りない。無借金経営が基本。自己資本比率が高い。
③利益を上げる最大の要素は、モノでなく、ヒトである。という考え。
どちらかと言えば、人使いが荒いと言われ、何でもやらせる、遊ばせない。
⑤「儲け」は、一気に大きくとるのではなく、細かく少しずつ積み重ねるものと、知っている。
⑥1回当たりの仕入れ量は、少ない。1品目当たりの仕入れ量も、少ない。
⑦仕入れや、経費の支払いは、「現金」が結局。得をすると知っている。
⑧ある単品、ある商品に圧倒的に強い。平均的な会社の倍以上、売っている。
⑨客層が明確である。一見しただけで「誰のための店なのか」すぐにわかる。
⑩独自の技術力に優れたものがある。他人が真似できないくらい、優れている。
⑪買ったときだけ一生懸命ではなく、買った後まで何かとサービスしてくれる、気にかけてくれる。
⑫見た目の奇抜さがある。店の外観や内装、商品作り、サービス、売り方等の面で、人をびっくりさせることが多い。
⑬経営者の人間としての考え方、理想・理念・哲学が、商品・販促・売場・スタッフに反映されている。
⑭役職者、ベテランほど良く働いている、一般スタッフは、それを目の前で見て、同じように働く。
⑮仕事の成果とその報酬が、かなり一致している。
ランダムに、箇条書きでまとめてみました。
どのくらい当てはまっていますか?